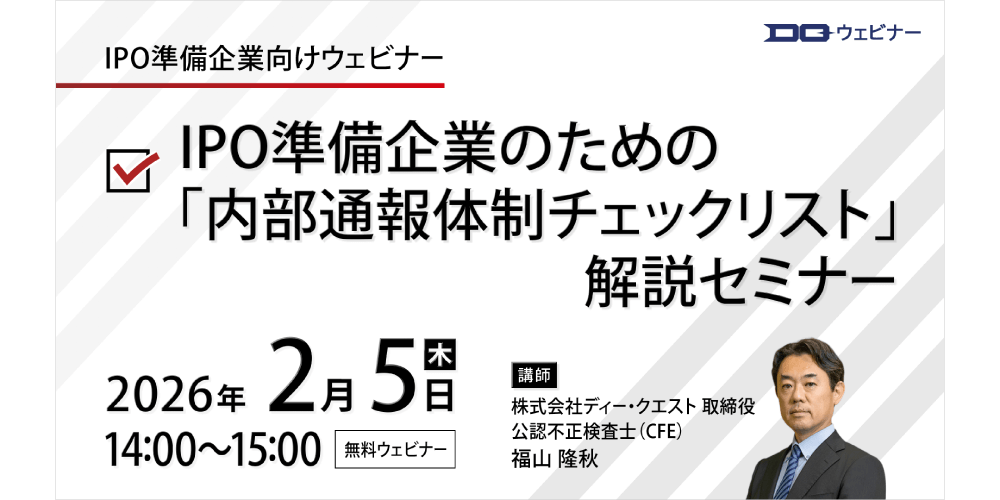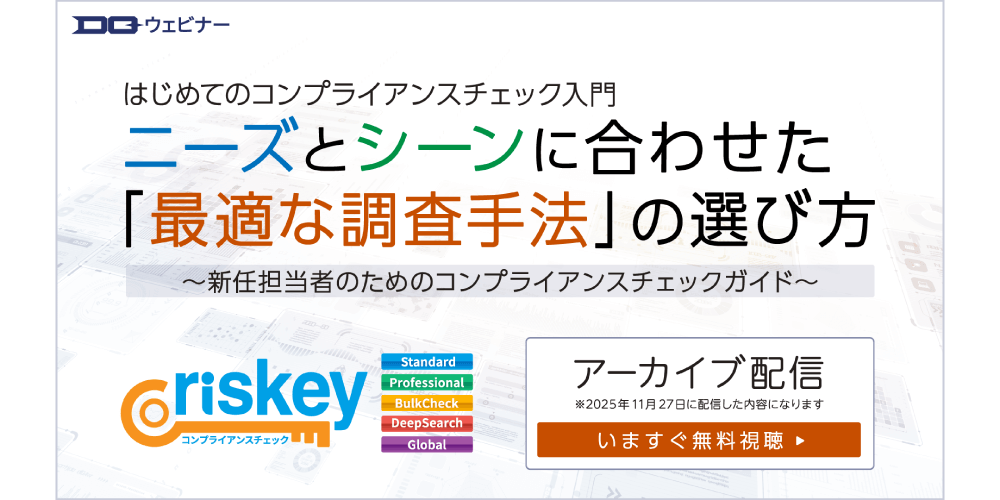商標・知財コラム 商標調査のスペシャリストのインターマークから、商標・知財コラムをご紹介
漢字プリンターとの出会い、採用
ある団体のOB会の情報交換会が不定期に開かれている。先日、久しぶりの開催があった。メンバーの中のT社出身のKさんから社史のコピーが渡された。前回、私がJPOの登録原簿の機械化の際、御社の漢字プリンターを採用したと話していた。そうしたら覚えていて頂いて、社史には、T社製造の漢字プリンターが記載されていた。
帰宅後調べると、私は、庁内の登録事務の機械化プロジェクトチーム(1974(昭和49)年10月設置)に2年程併任して、登録事務の機械化業務に従事した。その中で、記憶に残っているのが漢字プリンターの件である。
登録事務の機械化
先日、軽井沢から信濃追分を巡った(2023/6/19)。浅間山(2568m)の麓である。帰りの車中、「浅間山」を巡る事件を思い出した。「浅間山」は、商品の産地・販売地表示として拒絶された(32類 平成26.6.30 知財高裁平成25(行ケ)10332)。処が、「浅間山」は半世紀前には登録されていた(33.3.28 審判30-181)。その後、浅間山山麓地域は商業圏等としても発展したということであろうか。因みに、私の審査官修業時代、「阿寒湖」(31.11.26 抗告29-1468)は登録後審判で無効、「浅間山」は登録、何故かと研修の題材にされた。後者は山岳名とされ、前者は当時から観光特許庁の事務の機械化は、出願事務については1962(昭和37)年秋研究が開始されて、2年後に電子計算機を導入して、出願の処理状況管理が開始された。登録事務の機械化は、1964年着手されたが、開発に手間取り、登録事務の機械化プロジェクトチームは1974年10月設置され、その後の1977(昭和52)年10月に設定、移転、年金、原簿閲覧、謄本交付の各システムの運用テストが開始されて、1978(昭和53)年4月に機械処理が始まったとある(「工業所有権制度百年史」下巻714頁)。 当時すでに、特許法27条2項や商標法71条2項等が改正されて(昭和39年法律第148号)、特許原簿は、その全部または一部を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録して置くことができる物を含む。)をもって調製することとされていた。地として知られていたからだったと思う。雌阿寒岳(1499m)に登った時阿寒湖を遠望した(2011/6/12)。
続きは【商標・知財コラム】インターマークサイトへ

首都大学東京 法科大学院 元教授・元弁理士
工藤 莞司 先生
主な経歴
| 1969年 | 中央大学 第二法学部法律学科 卒業 |
| 1964年9月-2000年9月 | 特許庁(審査官、審判官等) |
| 2000年10月-2020年3月 | 弁理士登録、創英国際特許法律事務所 |
| 2004年4月-2008年3月 | 東京都立大学(現:首都大学東京)法科大学院 教授 |
| 2008年4月-2017年3月 | 首都大学東京 法科大学院 講師 |
主な受章・受賞
| 平成29年(2017年)春 | 瑞宝小綬章(通産行政事務功労) |
| 平成29年度 | 発明奨励功労賞 |
主な著書
| 1980年2月 | 「知っておきたい特許法」(初版~22版)財務省印刷局(朝陽会)共著 (特許法、不正競争防止法執筆) |
| 1991年8月 | 「商標審査基準の解説」(初版~8版)発明協会 |
| 1994年5月 | 小野 昌延 編著「注解商標法」青林書院出版 共著 (商標法4条1項10号~4条4項 執筆) |
| 2007年11月 | 「商標・意匠・不正競争判例百選」共著 別冊ジュリスト |
| 2012年5月 | 「不正競争防止法 解説と裁判例改訂版」発明協会 |