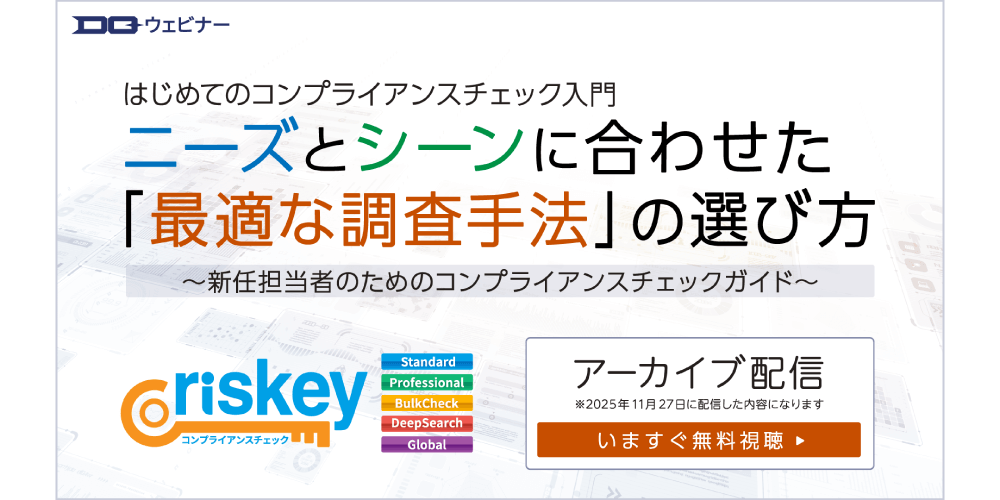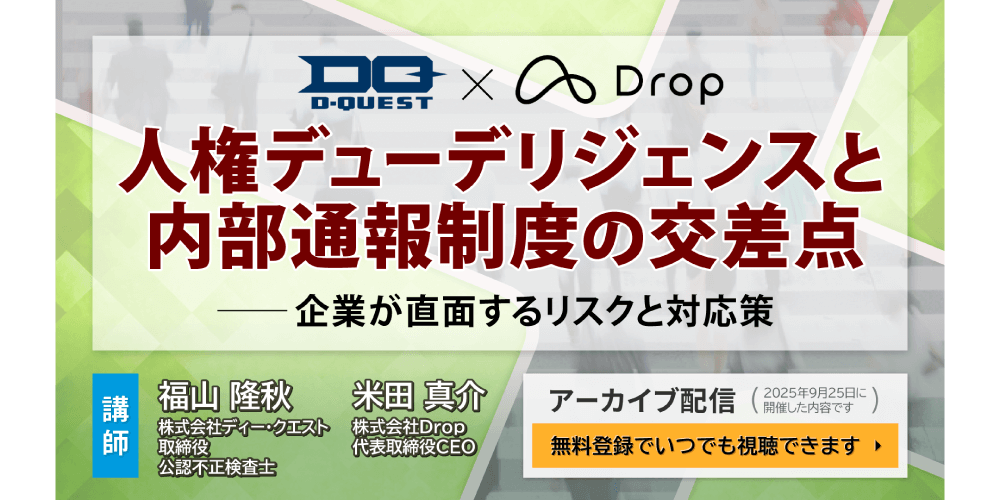DQトピックス
ガバナンス・リスク管理を実現する『経営者・実務者向け資料』のご紹介
2019.09.24
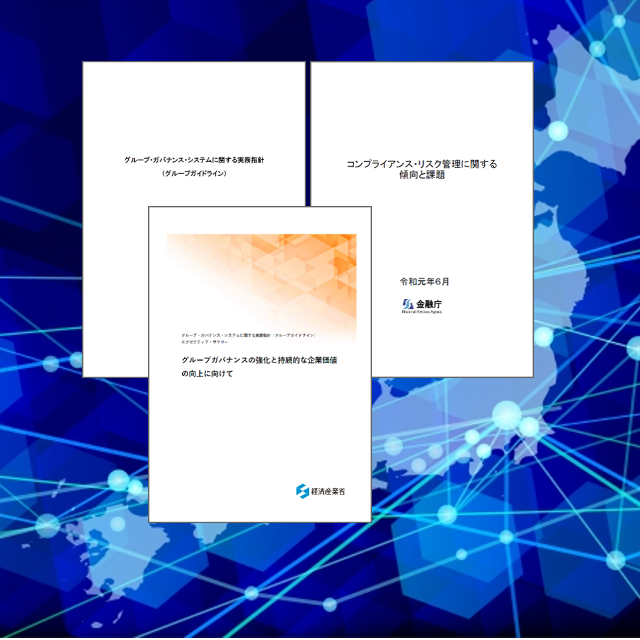
2000 年代に会社法 (2004 年) と金融商品取引法 (2006 年) が施行されてから、いわゆる「内部統制」「コンプライアンス」「リスク管理」に関する体制の整備が企業に対して求められるようになりました。
さらにその後、子会社・関連会社の不祥事や事故がグループ (企業集団) の価値を毀損する事例が相次いだことから、2015 年には会社法が改正されて、子会社も含めた企業集団としての体制の整備が法律で要求されるようになりました。
しかしながら、これらの体制をどのように整備・運用するのが適切なのか、経営者や実務者の立場にいる方は頭を悩ませることも多いことでしょう。
今回は、そのような経営者・実務者の方が手引き・参考にできる資料をご紹介します。
経済産業省「グループ・ガバナンス・システムに関する実務指針」(2019 年 6 月 28 日公表)
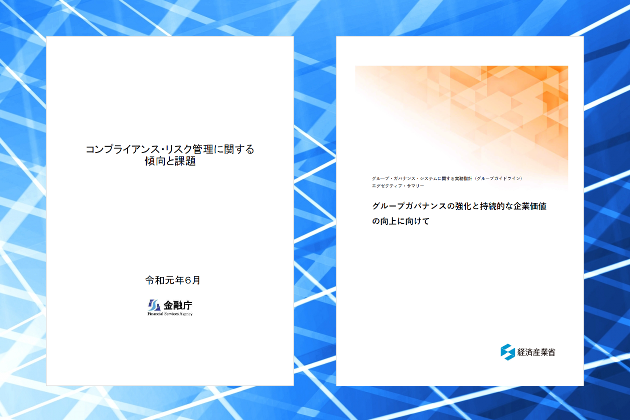
経済産業省が 2019 年 6 月 28 日に公表した「グループ・ガバナンス・システムに関する実務指針」は、グループ ガバナンスの実効性を確保するために、一般的に有意義であると考えられている具体的な行動や重要な視点が取りまとめられたガイドラインです。中長期的な企業価値向上と持続的な成長を実現するためのグループ ガバナンスの在り方について、ベスト プラクティス (最善策) が提示されています。
ガイドラインではひとつの独立した章として「内部統制システムの在り方」が取り上げられており、その中で「コンプライアンス」「不正防止」「リスク マネジメント」「サイバー セキュリティ」「有事対応」などにも触れられています。
ガイドラインは、グループ経営を行う企業を主な対象としていますが、それ以外の企業でも参考になる部分は数多くあると思われます。
特筆すべき点は、「本ガイドラインに沿った対応を行った場合には、他に特段の事情がない限り、通常は善管注意義務を十分に果たしていると評価されるであろうと考えられる。」(p.11) と記述されていることです。
取締役や部門責任者をはじめ、管理部門の実務者の方は、一読の価値があります。
ガイドラインは全体で 142 ページありますが、これを本文 20 ページに要約した「エグゼクティブ・サマリー」も公表されています。
- 「グループ・ガバナンス・システムに関する実務指針」を策定しました (METI/経済産業省)
https://www.meti.go.jp/press/2019/06/20190628003/20190628003.html
金融庁「コンプライアンス・リスク管理に関する傾向と課題」(2019 年 6 月 28 日公表)

金融庁が 2019 年 6 月 28 日に公表した「コンプライアンス・リスク管理に関する傾向と課題」は、金融機関におけるコンプライアンス リスク管理の取組事例や問題事象が取りまとめられた文書です。金融機関、証券会社、保険会社を中心に、経営陣との対話やモニタリングの結果から抽出された傾向や課題が提示されています。
この文書では、「経営陣の姿勢・主導的役割」「内部統制の仕組み」「企業文化」や、「事業部門」「管理部門」「内部監査部門」、「人材の確保」「リスクの捕捉及び把握」それぞれの着眼点から、「① 傾向と課題」「② 取組み事例」「③ 問題事象につながった事例」が整理されています。
金融機関に向けて公表された文書ですが、それ以外の企業でも参考にできる情報が多数掲載されています。
ガバナンス、内部統制、コンプライアンス、リスク管理に関わる方や、経営層・管理部門の方は、一読の価値があります。
- 「コンプライアンス・リスク管理に関する傾向と課題」の公表について:金融庁
https://www.fsa.go.jp/news/30/dp/compliance_report.html
ガバナンスやリスク管理の実効性向上のための取り組みのご紹介
今回取り上げた手引き・資料で触れられている取り組みの一部をご紹介します。(引用元は、経済産業省「グループ・ガバナンス・システムに関する実務指針」を「ガイドライン」、金融庁「コンプライアンス・リスク管理に関する傾向と課題」を「傾向と課題」と記載しています。)
内部通報
取り組みの一例として、次のような記述があります。
- ホットライン (内部通報制度) を通じて社内の人間が匿名でコンプライアンス部門に通報する仕組みを整えている。(ガイドライン p.80<参考:欧米企業の取組例>)
- ホットラインは海外子会社を含め全社的に整備されており、子会社の不祥事も本社の取締役会に情報が入ってくる仕組みとなっている。(ガイドライン p.80<参考:欧米企業の取組例>)
- コンプライアンス・リスク管理の実効性を高めるための内部統制の仕組みの一例として、(中略) 内部通報制度が活用されるべく、通報の適正な取扱いや通報者の保護に関する懸念を低減すべき (傾向と課題 p.6)
- 内部通報制度については、通報者の選択肢の幅を広げるべく通報窓口を複数用意する方法、匿名性を高める観点から外部の第三者へのアクセスを促進する方法 (中略) 等、企業価値を大きく毀損するような不正の防止に役立つ内部通報制度の確立に向け、利用促進やその実効性を高める方法を各社検討している。(傾向と課題 p.7)
- 子会社等における不正の端緒も把握すべく、親会社に直接通報が可能なグループレベルでの内部通報制度を整備 (傾向と課題 p.21)
「DQヘルプライン」は、これらの取り組みを実現いたします。
- 第三者通報窓口サービス「DQヘルプライン」
https://www.d-quest.co.jp/helpline/
公認不正検査士 (CFE; Certified Fraud Examiner)
取り組みの一例として、次のような記述があります。
- 管理部門や内部監査部門を実効的に機能させるため、経営トップは、これらの部門の重要性を認識し、中長期的な人材育成や、専門資格の取得等を通じた専門性やプロフェッショナル意識の向上を図るべきである。(ガイドライン p.88)
- 管理部門には、事業部門のビジネスについて経験や知識が豊富な者だけでなく、特定分野 (法令、反社会的勢力対応、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策や金融犯罪対策、複雑な金融商品、クロスボーダー取引、IT、サイバーセキュリティ等) に精通したスペシャリストを幅広く採用・配置している (傾向と課題 p.23)
ガイドラインでは、専門資格のひとつとして、ACFE が認定する「公認不正検査士 (CFE; Certified Fraud Examiner)」が取り上げられています。(ガイドライン p.89 脚注 85) また、公認不正検査士 (CFE) 資格を取得する要件のひとつである資格試験の合格には、傾向と課題で挙げられた特定分野の知識が要求されます。
より実効性のある内部統制・不正対策のために、公認不正検査士資格をご利用ください。
- 一般社団法人日本公認不正検査士協会 (ACFE JAPAN)
https://ACFE.jp - CFE (公認不正検査士) について
https://ACFE.jp/cfe/cfe-about/what-is-CFE.php