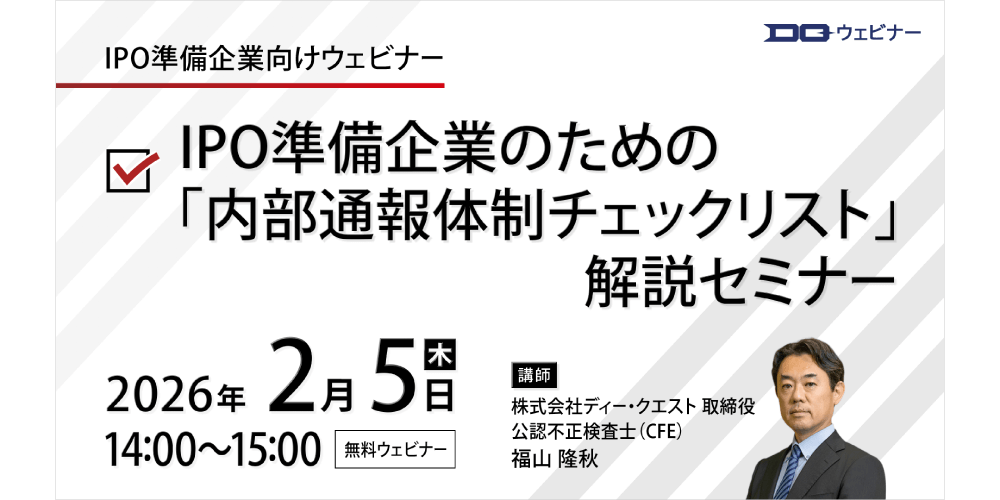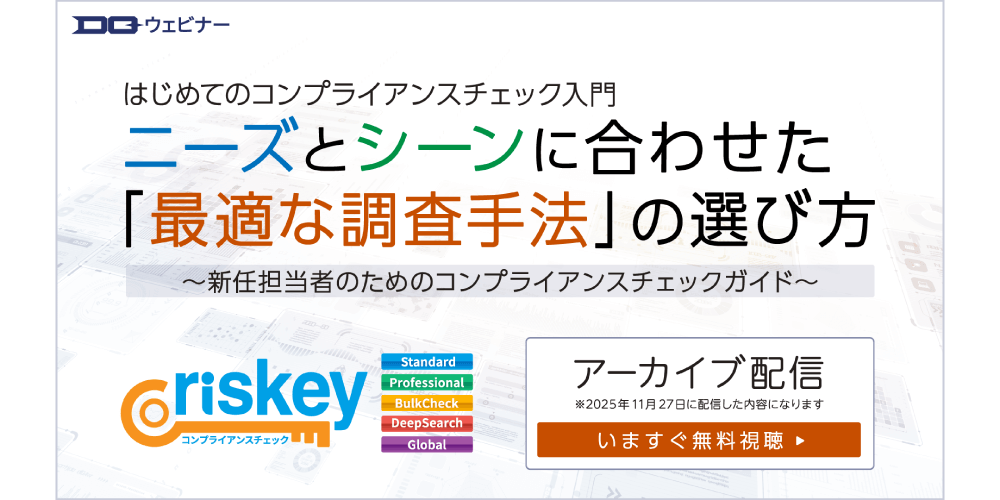DQトピックス
企業不祥事発生時の対応と記者会見での留意点~ リスクマネジメント・マスコミ対応の心得~
2020.05.07

もくじ
1.はじめに

経済のグローバル化に伴う市場競争の激化、グローバル基準に沿った公正な企業活動への社会的要請、国際紛争に絡むテロリスク、倫理経営重視の社会的評価基準、雇用形態の多様化に伴う従業員の帰属意識の希薄化、セクハラ、パワハラなど人権に絡む新たなリスク、不祥事に対する罰則強化と社会的糾弾激化、並びにそれらに対応しての新たな取締法規の制定など、企業経営を取り巻く環境は、20世紀と21世紀とでは、将に、大きく様変わりしている。企業規模の大小にかかわりなく、不祥事発生時の対応(クライシスマネジメント)を誤ると、各種行政罰、上場廃止、高額賠償訴訟、社会的なボイコット運動、風評被害などで企業は壊滅的な影響を受け、最悪の場合、倒産や市場からの撤退を余儀なくされる事態となる。
リスクマネジメントプラン策定の一助となるために、企業における不祥事発生時の対応上の留意点と記者会見における具体的な注意事項について筆者の経験に基づいて説明する。
2.企業不祥事対処の基本的姿勢
(1)露見して大問題になる前に、極力公表するなど「先制攻撃」を心掛ける。

不祥事や事故などのリスクが発生したときの一番重要なポイントは、「正直・迅速対応」である。内部告発などにより事実が公となり、大問題となる前に、リスクに関する報告を受けた場合には、極力、迅速に事実の公表や、監督官庁への報告を行うことが大切である。「何とかなるだろう」「隠し通せるだろう」といった安易な考えから、不祥事を隠蔽する姿勢は、結果的に状況をさらに悪化させ、最悪の場合、企業の存続そのものを脅かす事態となる。典型的な事例としては、上場の大手総合電機メーカーによる長年にわたる不適切な会計処理事件や、耐震ゴムの性能試験データ改竄についての組織ぐるみ隠ぺい事件、名門の化粧品会社による“白斑禍”事件への対応遅れによる被害の甚大化や、最近では、武漢で発生した新型コロナウイルス事件の公表遅れや、感染者数改竄疑惑などで世界中から厳しく糾弾されている中国の例などがそれである。将に「初期対応の良し悪しが 天国地獄の 分かれ道」である。
(2)迅速なる「リスク対策チームの設置」と「情報管理の一元化」を図る。
企業不祥事に対する社会的な厳しい風潮を反映して不祥事が発覚した企業に対しては、マスコミなどからの取材や記者会見で、事実や責任の所在など厳しく追及される。不祥事が発生した場合、最初にやるべきことは「リスク対策チーム」と「情報管理の一元化」である。前者で留意すべきは、マスコミ・被害者・監督官庁への対応、原因分析、再発防止策の検討などに的確に対応でき23るメンバー選定と、後者では、従業員や関係者からの誤った情報や誤解を受けるような情報発信を防ぐための情報発信窓口の一元化である。将に、「無用の混乱防ぐには 情報窓口 一元化」である。
(3)現在起きている事実、事象を極力多く集めること。
迅速なる事態の収拾を図るためには、正確な事実関係の掌握が必要不可決である。事件関係者からの事情聴取で留意すべきは、事情聴取者の人選である。その場合、事件当事者の上司など直接的な利害関係者に担当させないことである。上司も弱い人間、事情聴取にあたっては、つい、犯罪者を取り調べるような尋問口調・責任追及姿勢になり、自分に不都合なことは隠すなど真実の解明を阻害する要因となりがちである。事態の早期解決のためには、被聴取者本人から信頼され、全面的な協力を引き出せる人材を選任することが特に重要である。
将に「正確な 事実の情報聴取こそ リスク対処の 第一歩」である。
(4)マスコミ対応は「正直・誠実・オープン」を原則とする。
マスコミ対応において留意すべきは、マスコミを敵視するのでなく、「正直・誠実・オープン」の姿勢で臨み、味方にすることは出来なくても、少なくとも敵対関係だけにはならない様に心掛けることである。記者会見を忌避するのではなく、「会社の誠実な対応や、正確な事実関係を社会のより多くの皆様にご理解頂く絶好のチャンスである」と前向きに受け止め対応することが重要である。例えば、某大手家電メーカーで発生した「石油ストーブ不完全燃焼による死亡事件」では、当該企業による長期にわたるテレビ謝罪広告や、真摯な製品回収努力が一般消費者から高く評価され、むしろ株価が上昇した例もある。
将に「誠実・真摯な対応で 災い転じて 福となす」である。

(5)トップが「現地・現物・現認」を心掛け、陣頭指揮を執ること。
事件発生時におけるトップの「率先垂範」による「陣頭指揮」と積極的な対応が重要である。中でも、対処方針の迅速なる決定と明示、記者会見などは、部下任せにせずトップ自らが率先してこれにあたる。更に、トップとして事実についての正確な情報入手のために、自ら現地に赴き、「現地・現物・現認」を実践することも大切である。記者会見の場でも「社長は、実際に現地に出かけて確認したのか?」と質問されるケースも増えている。ご承知のように、不祥事に対する世間の眼は年々厳しくなっており、記者会見の場に社長が出席するのと、専務・常務が出席するのとでは、記者会見への社会的評価や印象が大きく違うことを十分認識しておくこと。
将に「記者会見 判るトップの 危機意識」である。
3.危機発生の最中に絶対やってはいけない10のポイント
4.記者会見における基本3原則

- 記者会見は、基本的には、トップ自らが対応すること。(誠心誠意の姿勢)
- 記者会見で、言えることと、言えないことをきちんと整理しておく。(混乱防止)
- 記者会見中の取材拒否、ノーコメント乱発、嘘、憶測発言はしない。(マスコミ対応の厳禁事項)
5.マスコミ対応の心得十か条
第一条:「記者会見は、企業の対応方針や、考え方を直接、消費者やお客様に伝えるための絶好の機会として捉えて、トップ自らが、正確な事実を理解・認識したうえで、積極的に対応する。」
第二条:「正直・迅速な対応を基本に、責任回避と受け止められるような発言や、安易な憶測発言は厳に慎む。」
第三条:「事故や不祥事発生に対しては、真心のこもった遺憾の言葉や、お詫びの言葉を表明する。」
第四条:「事件発生の経緯や原因調査結果の最新情報については、判明次第、逐次、正直に公表する。」
第五条:「被害者や遺族などへの対応や補償については、誠心誠意の姿勢であたることを表明する。」
第六条:「責任問題については、事実の解明と、調査結果にもとづき適切に対処することを表明する。」
第七条:「問題解決・再発防止に向けての企業としての具体的方針や現在進行中の取り組みについて、マスコミを通じ、積極的にPRして企業努力に対する理解を求める。」
第八条:「マスコミや被害者からの質問・意見・要望については、誠意を以て極力、迅速に対応する。」
第九条:「記者会見での記者からの質問に対しては、常に真摯な態度、誠実な姿勢での対応に心がける。」
第十条:「記者会見での記者からの質問に対しては、常に真摯な態度、誠実な姿勢での対応に心がける。」
6.記者会見での一般的な注意事項

- 記者会見を無事に終わらせることを第一に、質疑応答などで感情的にならずに、常に正直で誠実な態度を心掛ける。
- 記者会見で公表する事実関係については、必要に応じて、事前にシナリオを作成し、会見場での出席者間の事実関係の認識に齟齬が発生しないようにしておく。
- 記者会見におけるメインスピーカーは極力一人に絞り、他の者は、特に、質問受けた場合以外は積極的に発言しない。
- 記者からの質問で、明らかに事実と違っている場合で、当方への影響が大きいものについては、看過せず「一言補足説明をさせて頂く」と断ったうえで、ポイントを簡潔に述べる。
- 記者会見で責任転嫁や自己弁護のみの印象を持たれるような発言は避け、安易な期待や根拠のない憶測発言は厳に慎む。
- 記者会見会場には、カメラで映されたり、その資料をいただきたいと要求される恐れがあるので、Q&Aの資料は持ち込まない。
- 基本的には一問一答を原則に、発言内容は、極力、シンプルに事実のみを述べる。
- 記者からの再三の突込み質問に対しては、Q&Aに則り、再度簡潔に繰返し説明する。
- 記者からの挑発的な質問や、ひっかけ質問、特殊な専門的質問に注意する。特に仮定の質問や、企業秘密に関わる質問、セキュリテイに関わる質問には十分注意すること。
- 記者会見での応答では、言葉は丁寧に、服装は地味に、表情も冷静に、誠実な態度で、記者の方をきちんと見ながら答える。
7.記者会見会場の設定とその他具体的な注意点
【1】記者会見会場の設定と会場準備
- 日頃から万一に備えて会場設定の候補場所について調査しておく。
- 当方にとって対応しやすい場所を設定する。社外か社内かは状況により判断する。
- 会場は、ゆったりしたスペースを用意し、記者席を通らぬ退場口を確保しておく。
- 記者席は、多めに確保する。ライバル会社と近付き過ぎないように配慮する。
- トイレは社内関係者用とマスコミ関係者用は別にする。情報漏洩、トラブル防止。
- テーブルを前にしてテレビ取材や記者会見を受ける。司会者の場所は広めに確保。
- 回転椅子やキャスター付きの椅子は不安定なので避ける。
- 開始時間は、カメラの設置に時間がかかることを考慮して決める。(約20~30分)
- 会見中に電話が鳴ったり、会見場所にむやみに人が入って来ないようにする。
- 室温調整に十分配慮する。事前に少し寒い程度にしておく。
- 会場は質素に、花などの装飾は無用。

【2】記者会見に臨むための服装・身だしなみ
- スーツは、ダーク系、現場での会見なら作業着でも可。
- ワイシャツは、白か薄いグレー又はベージュのシングルカラー。
- ズボンは、きちんと折り目のついたものを着用。
- 靴下は、黒か紺色。靴は、黒靴で、きちんと磨いておくこと。
- 眼鏡は、縁が派手な色のものや華美なものは避ける。
- 髪型は、清潔感のある髪型。フケなどには注意。
- 時計は、反感やテレビで映されることも考えて、超高級品や華美なものは避ける。
【3】記者会見中の態度と話し方
- 質問には、誠意ある態度で答える。
- 自信のあるようなゆっくりとした自然な態度を心掛ける。
- Q&Aでは基本的にはメモを見ない。但し、データの確認は、その旨伝えて行うこと。
- 椅子には深く腰掛けて、背筋を伸ばし姿勢良くしておく。
- 眼鏡を外したり、かけ直したり、マイクを触ったりしない。落ち着きがない印象を与える。
- 両手は軽く握って机の上に置く。腕組は厳禁。
- 会見中はやたらに腕時計を見ない。早く終わらせたいと相手に思われる。
- 話すときは、マイクに口を寄せる動作をしない。
- 質問に答える際は、相手の顔を見ながらゆっくり話す。きょろきょろ視線を動かさない。
- 声は、出来るだけ柔らかく、普通のトーンで話す。
- 回答は、出来るだけセンテンスを短くして、ポイントを簡潔に話す。
- 不意の予想外の質問にも慌てずに怒りや困惑顔をしない。
- 一つの質問に対して回答は長くても30秒~40秒程度とし、結論を先に述べ、次に要点を手短にコメントする。
8.終わりに―筆者からのメッセージ:「企業経営」=「リスクマネジメント」
企業経営に必須の4つの資源、「人・もの・金・情報」の全てにリスクが存在している。
事業を行っている以上、不祥事発生リスクは避けることは出来ない。その観点から申せば、将に、「企業経営」=「リスクマネジメント」といっても過言ではない。
リスクマネジメント(危機管理)の基本は、リスクの存在を正しく認識することから始まる。変化の激しいグローバル時代においては、コンプライアンス経営は、企業存続のための最低限の条件だと言える。経営者は、常に、事業運営のプロセスに存在する不祥事リスクを意識し、万が一に不祥事が発生した時に如何に対処するかを意識しておくことが重要である。日本の企業では、不祥事を起こさないための従業員教育や不祥事防止対策には熱心だが、いざ、不祥事が発生したときに備えてリスクの影響を如何に最小限に抑えるかについての教育や対策に欠けている面が多いように感じる。
将に、不祥事への「初期対応の 良し悪しが 天国・地獄の 分かれ道!」である。
最後に、リスク対処心得を標語にした「リスク対処心得“8イング”!」をご紹介する。
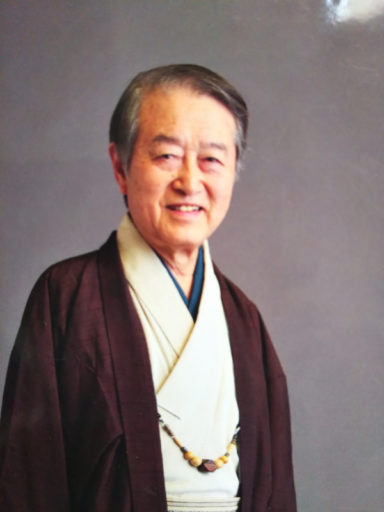
昭和16年 福岡県福岡市生まれ。鎌倉在住。
福岡県立修猷館高校、早稲田大学法学部卒業後、昭和40年、日立製作所に入社。
労務、人事、総務畑に従事し、本社勤労副部長、情報事業部次長などを経て日立製作所理事を歴任。
平成12年、日立電子サービス(現、日立システムズ)に転属し、専務、常勤監査役を歴任。
平成19年、同社退社後、企業リスク研究所を設立。同代表、経営塾「白木塾」塾長、日本総合危機管理 特別顧問、東京福岡県人会理事、鎌倉ユネスコ理事、鎌倉市倫理法人会副会長などを務める。
白木家始祖は越前国主・朝倉義景の弟、朝倉景遠、黒田藩筆頭家老・栗山利安の末裔。