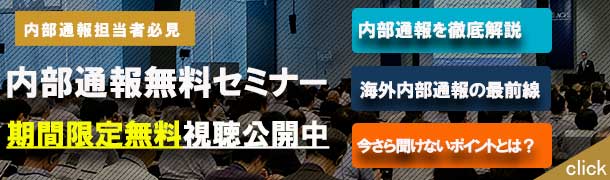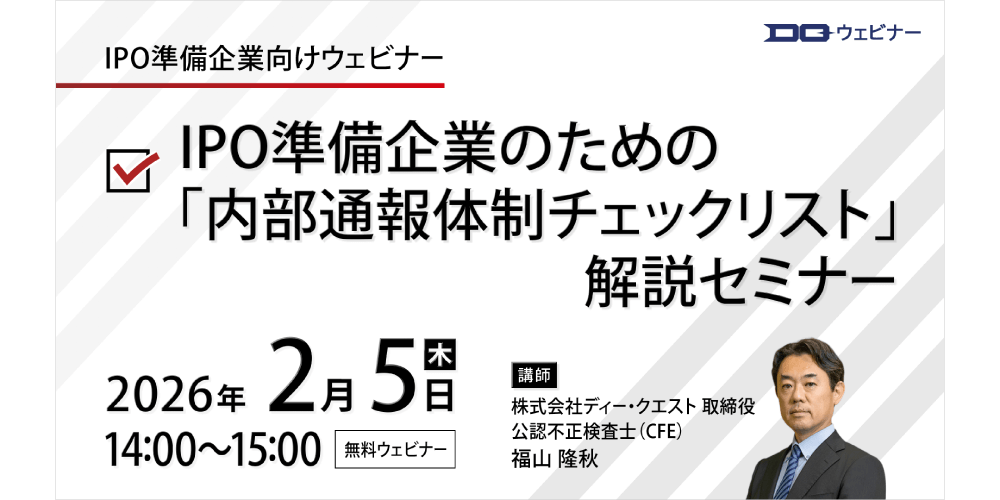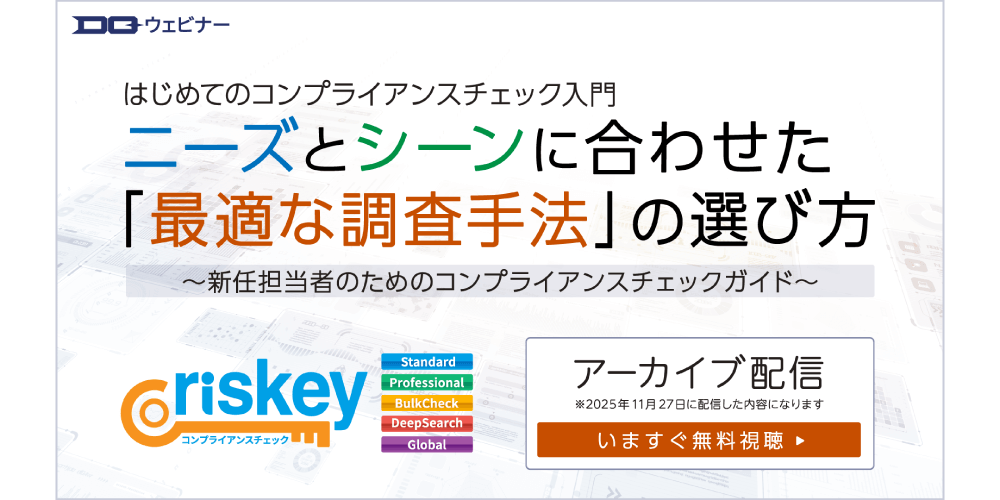DQトピックス
Governance Q【磯山友幸×八田進二#1】ガバナンス敗戦「失われた30年」の取材風景
2023.11.30

八田進二・青山学院大学名誉教授が各界の注目人物と「ガバナンス」をテーマに縦横無尽に語り合う大型対談企画。シリーズ第10回目のゲストは、経済ジャーナリストで千葉商科大学教授の磯山友幸氏。日本経済新聞の記者としてバブル期における日本企業の乱脈経営の取材を皮切りに、主にマーケット、会計制度などの分野で表裏両面から日本経済の「失われた30年」を取材してきた。そんな硬派ジャーナリスト、磯山氏の考えるガバナンスの実相とは――。
取材の原点はバブル不祥事と国際会計基準
八田進二 磯山さんとは日本経済新聞の記者だった時に取材を受けて以来、ずっとお付き合いをさせていただいています。現在も“硬派ジャーナリスト”として、そして大学教授として活躍されていますが、ガバナンスに強い関心を抱かれたのには、どういう経緯があったのでしょうか。
磯山友幸 僕の記者人生というのは、今で言う「ガバナンス」の問題と一緒に歩んできたようなところがあります。日経に入社したのが1987年で、最初に大阪に配属されました。まさにバブル経済真っ盛りの時期。特に大阪では酷かったのですが、いわゆる裏世界の住人たちが表に出て来て、企業にどんどん侵食していった。代表取締役の座を簒奪したり、手形を乱発してその会社の不動産を売却したり……。仕手筋などが帳簿閲覧権行使や株主代表訴訟など、商法などの知識をフルに使って上場企業を食いものにしていくのを目の当たりにしました。
八田 当時の経営者からすると、想定外の出来事だったかもしれませんが、そもそもはマーケットの問題。株式を取得した以上、誰にでも株主の権利があって、どうやって株主に利益還元をしていくかということです。ただ、バブル期以前の日本の経営者にはその点で危機意識がありませんでしたよね。シャンシャン総会に象徴されるように、慣れ合いの中で経営がなされてきたので、裏社会の住人たちが直接的に企業を侵食してくることに免疫がなかった。
磯山 そうですね。当時、社長は企業においてオールマイティーで、何でもできるという感覚がありました。一方で、株式の持ち合いなどがあって、株主も形式的な存在でしかありませんでした。ガバナンスの議論など全くなくて、「社長が全てを決められるのが会社だ」というのが当たり前の時代。それに目をつけたのが裏社会で、代表取締役の判子さえ押されていれば何でもできる。そうやって上場企業で不祥事が相次ぎました。
続きはGovernanceQへ