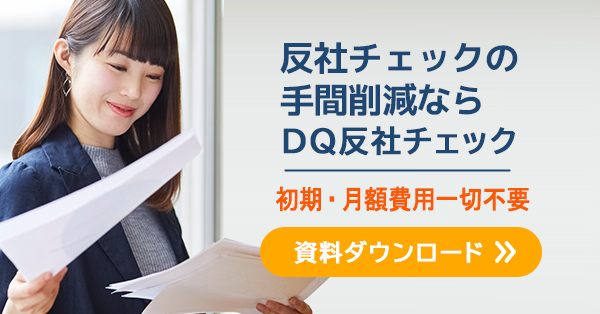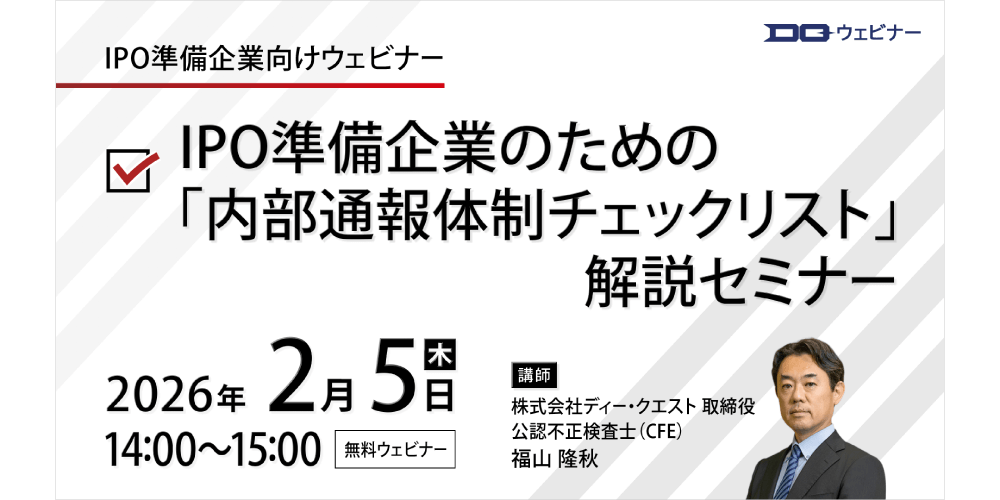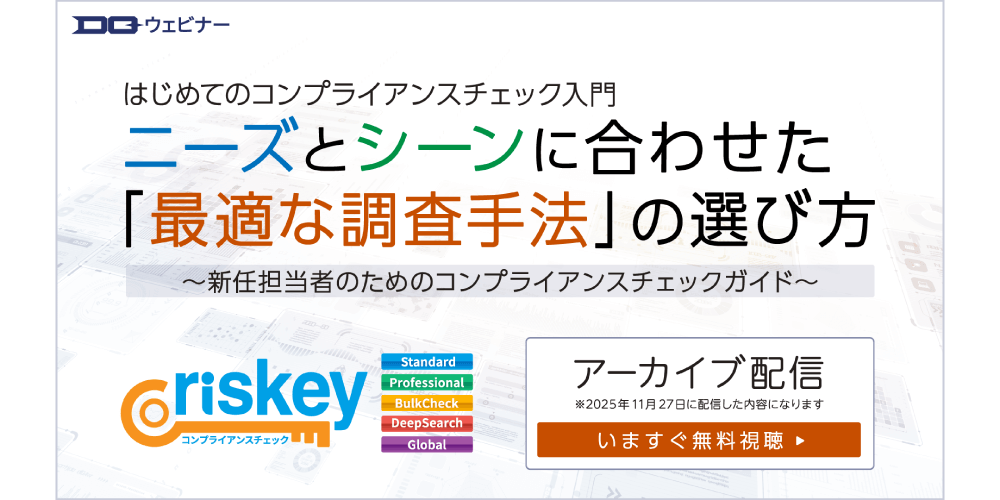DQトピックス
Governance Q 今さらの「政策保有株削減」に経営改革は期待できるか【ガバナンス時評#19】
2024.07.24

3月末までに開示された東証プライム上場企業のコーポレートガバナンス報告書を集計したあずさ監査法人によると、プライム企業(1650社)のうち、1348社が政策保有株式や、いわゆる「持ち合い株」を保有。トヨタ自動車、伊藤忠商事、大日本印刷などをはじめ、プライム企業の7割に当たる1095社が政策保有株の削減方針を打ち出しているという。
政策保有株式とは、企業が他社との取引上の関係などを構築・維持するとの名目で保有している株式を指す。特に相互に政策保有株式を持っている場合には「持ち合い株」と呼ばれる。
保有目的が「取引関係の構築・維持のため」とは聞こえはいいが、実際には金融機関が融資先企業の株を保有するなど、利益相反になりかねないケースも少なくない。こうした政策保有株式のあり様は、長らく日本の資本市場の特異性を象徴するものとされてきた。
それがなぜ今になって、全体で約60兆円(2024年3月期末時点)とも言われる政策保有株の削減が目立っているのか。それには3つの理由がある。
政策保有株を売却した方が「経営効率は向上」
1つ目の理由は、コーポレートガバナンスの浸透である。
そもそもアメリカでは1930年代に制定されたグラス・スティーガル法により、解釈には幅があるものの、基本的に銀行は商業銀行業務(融資)と、投資銀行業務(証券)の分離を義務付けられてきた。そのため、金融機関が融資先の株を「買い支える」ことには、利益相反問題および市場倫理における懸念があるのだ。
これまでの我が国の企業習慣では、いわば“お付き合い”を口実とした政策保有株の持ち合いにより、低配当の株式を持ち続けることが事実上、許されてきた面がある。本来、正当な株主利益を擁護するために厳しい経営の監視がなされなければならない企業の投資活動が、リスクを取らない“もたれ合い”となっていることに対する非難が長く燻ってきた。
また、政策保有株については「持っていることによる利益率、企業の安定的な成長率の高さ」を建前に説明してきた企業もあるが、近年の研究ではむしろ「売却後のほうが利益率・成長率が高い」との分析もある。
80%を超えるプライム企業が政策保有株を持っていたこと自体に驚かされるが、これは結果的に、生え抜きトップによる経営の安定化を図り、敵対的な買収防衛にも資するためであろう。逆に言えば、真の意味で市場の論理に従った経営をしてこなかった証左でもある。安定的とはいえ、ぬるま湯体質の中で低配当の投資行為を許してきた日本市場、経営者の責任は免れない。
続きはGovernanceQへ