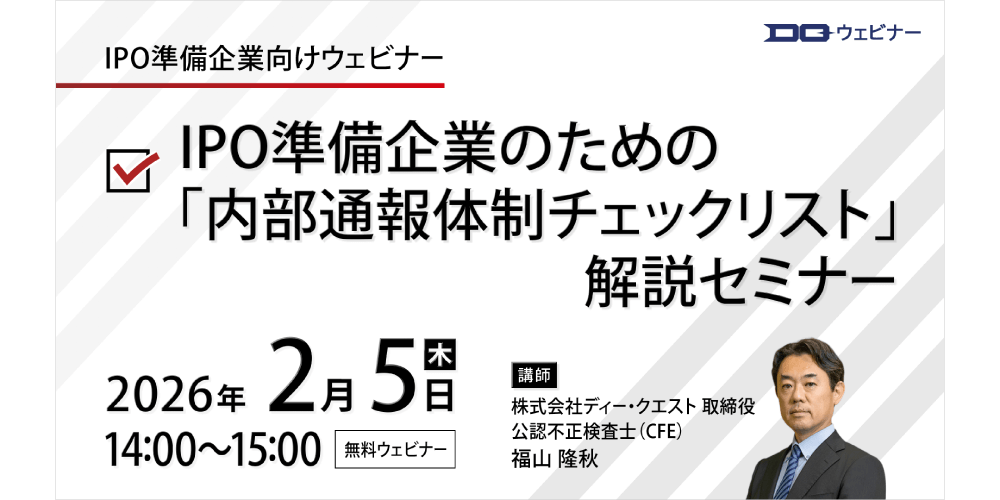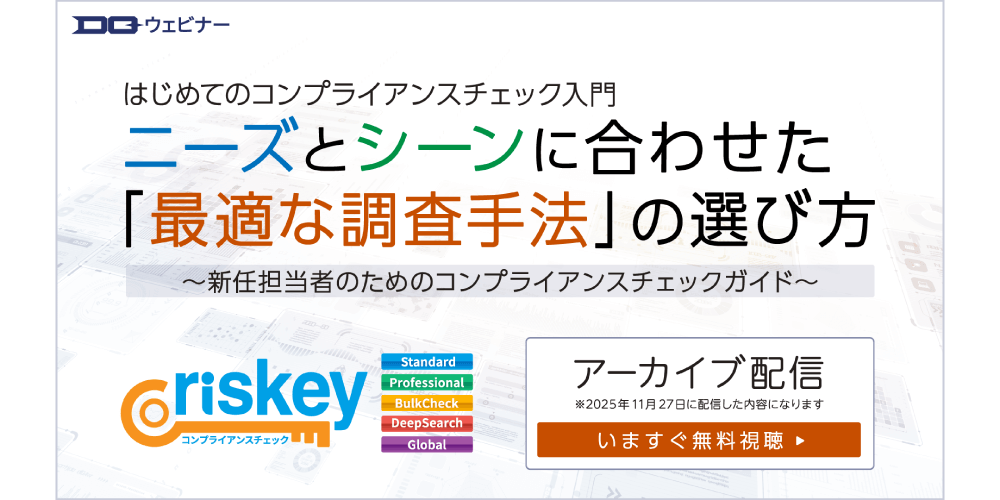DQトピックス
Governance Q【ACFE JAPAN岡田理事長インタビュー後編】不正対策で公認不正検査士が果たす役割
2024.04.11

(インタビュー前編から続く)昨年、『監査役の矜持――曲突徙薪(きょくとつししん)に恩沢なく』(同文館出版、朝日新聞記者の加藤裕則氏との共著)を上梓した日本公認不正検査士協会(ACFE JAPAN)理事長の岡田譲治氏。監査役およびリスク管理部門の実際とあるべき姿についての前編に引き続き、後を絶たない企業不正、監査役の不作為、そして、不正・不祥事案における公認不正検査士(CFE)の役割などについて語ってもらった。インタビュー後編。
日本企業で不祥事が相次ぐ“温床”とは
――最近でもトヨタグループ各社の品質不正問題など、大企業の不祥事が後を絶ちません。今の状況について、どのようにご覧になっていますか。
三井物産の常勤監査役だった2017年に公益社団法人日本監査役協会の会長になり、翌18年と19年の4月に開催した全国会議では「企業不正」をテーマに取り上げました。ただ、私が会長を辞めた後もまた、全国会議で同じような問題を取り上げています。企業は変われども、今もなお名の知られた大企業が次々と不正を引き起こしている状況ですね。
不正や不祥事の中身は多種多様ですが、最近では特に品質不正に注目が集まっています。日本を代表するものづくり企業で品質不正がなぜ絶え間なく起こるのか。そのことを考える時、私は背景に日本企業の特徴である「前例踏襲」主義があるのではないかと思っています。初めは誰かがイレギュラーな形で不正を犯したものの、それが社内で問題視されないと、不正自体が前例として長く踏襲されるのではないかという問題意識です。
これと関連しますが、日本企業では、専門性の高い部門では人材にあまり入れ替わりがないという環境があります。異動がなく、ひとつのポストにベテランの担当者を張りつけっ放しにする。そういう状況が続くと、外からの意見を聞かなくなるし、専門外の人は意見を言えなくなります。ごく稀に新任の人が「何かこれ、おかしいのではないですか?」と言っても、黙殺されてしまうのです。結果、そんな外から来た人が外部へ内部告発して初めて不正が表に出る――そのようなケースが往々にしてあるのだと思います。
続きはGovernanceQへ