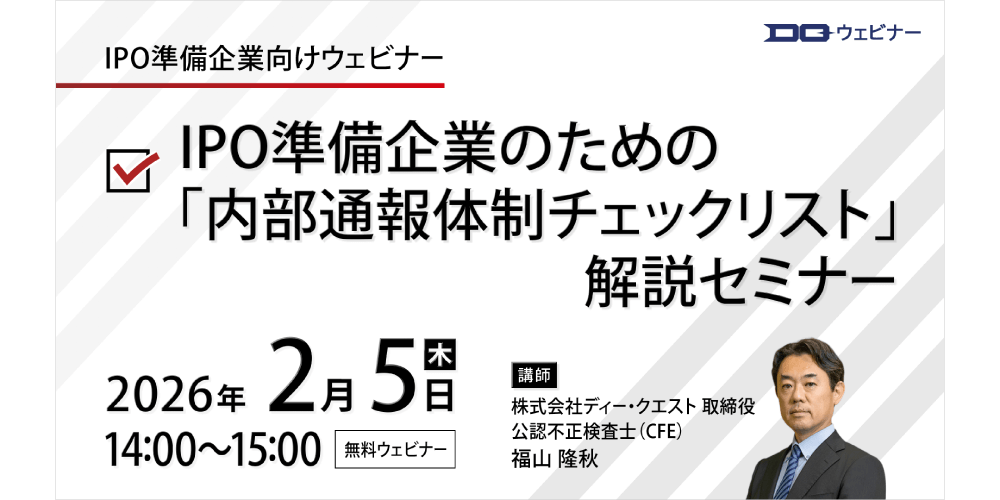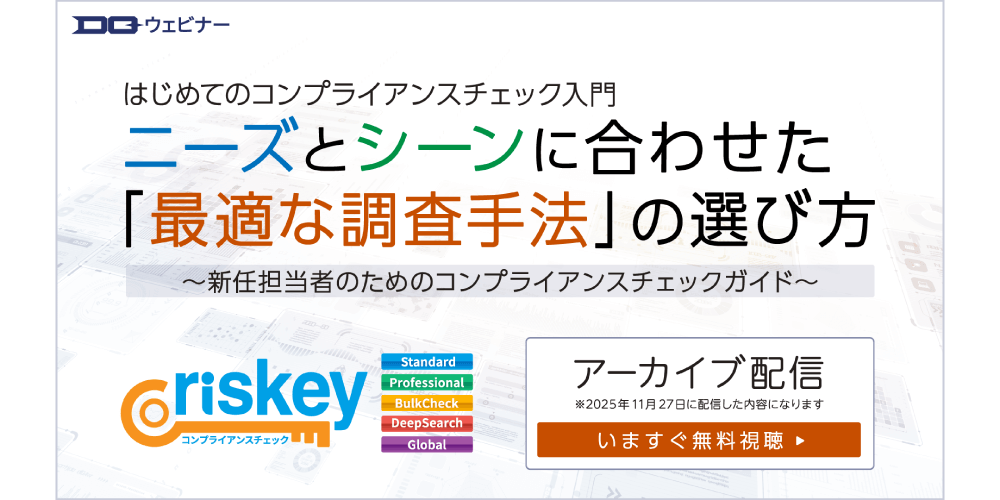DQトピックス
樋口先生の「失敗に学ぶ経営塾」WEB講座:第4回 調査委員会の機能不全ー関西電力のコンプライアンス違反事件
2020.09.23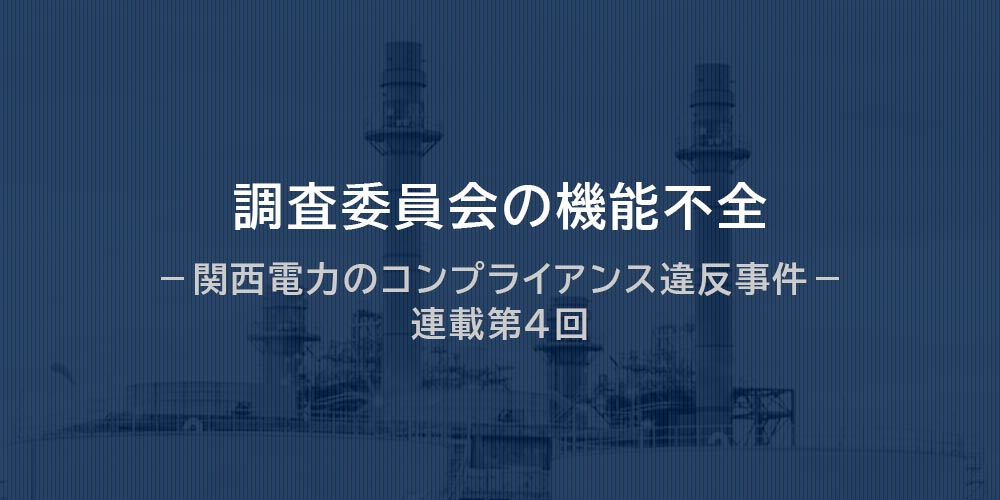
もくじ
1.事件対応の経緯

M氏に対して国税局の調査が行われていることを関電側が認知したのは,2018年1月30日のことだ。翌2月には, 甲会長・乙社長・X1~X3氏が受領していた金品をM氏に返却し, 6月には調査委員会が設置された。9月に調査報告書を受領した甲会長と乙社長は,本事件を公表しないとの方針を決定し, 翌10月には,情報漏洩のリスクを避けるために取締役会にも報告しないことにした。
かくして社内で実質的に隠蔽する形となったが, 2019年9月26日にマスコミ報道により本事件が発覚した。翌27日に乙社長が記者会見を行ったが,受領者の氏名や受領金額等の情報公開に消極的な姿勢を示したことから火に油を注ぐ結果となった。
10月2日には甲会長と乙社長が再度の記者会見を開き,調査報告書を公開するとともに謝罪した。また,調査報告書の内容が会社寄りで,調査範囲も狭いと批判されたことから,中立・公正な社外委員で構成される第三者委員会の設置を決定した。甲会長は10月中に辞任し,乙社長も翌年3月の第三者委員会報告書の発表に合わせて辞任した。
関電の役職者が多額の金品を受領したことが,コンプライアンスに反することは明白である。本事件を速やかに公表するとともに,社外取締役など外部の力を活用して実態の解明に当たることが必要であった。しかし実際には,前述した対応により関電に対する不信感を一層強め,厳しい批判を受ける結果となり,不祥事の収拾という危機管理に失敗したと言わざるを得ない。
自らも受領者であった甲会長と乙社長に,「できれば事件を非公表にしたい」とのバイアスがかかるのは当然であるが,その判断ミスを助長した背景として,調査委員会の機能不全と相談役の不適切な助言が挙げられる。
2.調査委員会の機能不全

調査報告書は,「原発の運営のために,M氏の無理な要求に従わざるを得なかった被害者」という情状を強調し,「関係者の取った行動は不適切であるが違法ではなく,情状面を勘案するとそれほど重大ではない」と認定した。本事件を非公表とする方針を決めるに当たり, この調査報告書の見解が大きく影響した。
この他にも調査委員会には,以下のような数々の問題点が認められる。
- 調査の時間的範囲と人的範囲を絞り込んだこと
- まだ存命だったM氏にヒアリングしなかったこと
- 原子力事業本部を通じて社内のヒアリングを実施したこと
- 特別関係企業との取引について十分に調査しなかったこと
- M氏への発注約束を看過したこと
あらためて第三者委員会を設置し,本事件の再調査を行わせたのはそのためである。
率直に申し上げて,調査委員会側に徹底した調査をする意思が存在したかどうか疑わしいと言わざるを得ない。その背景として,弁護士3人・関電の執行役員3人の計6人で調査委員会が構成され, 第三者的立場を担保していなかったことが挙げられる。近年,不祥事調査のために設けられた機関が会社側に忖度して調査結果を歪めてしまう問題が散見されることから,この機会に猛省を促したい。
3.相談役の不適切な助言

本事件を非公表とする方針や,本事件を取締役会に報告しないとする方針を決めるに当たって,甲会長と乙社長は,相談役の丙氏に相談していた。丙氏は,かつて関電の社長・会長を歴任した先達である。
日本企業では,このように元経営幹部が相談役あるいは顧問などの立場で重要な意思決定に関与しているケースが珍しくない。終身雇用制度により経営幹部が生え抜きであるため,元経営幹部と現経営幹部の間に,先輩と後輩,上司と部下という人間関係が染みついているのであろう。
しかし,そもそも経営責任を問われない者が実質的な影響力を行使することが,企業統治の面から不適切であるのは言うまでもない¹。特に本事件のように過去の経緯を引き摺った問題に対処する場合,元経営幹部は現役時代の経営責任を問われるおそれもあることから,問題の矮小化さらには隠蔽を使嗾(しそう)する可能性が少なくないと考えられる。
実は, こうした相談役・顧問の問題について, 海外の機関投資家も注目し始めており, 早晩対応を迫られることになろう。筆者のアドバイスとしては,内規や申し合わせの形で,元経営幹部を相談役等に任用しないことを確認すべきである。その一方で,元経営幹部の知見や人脈が求められるケースも否定できないことから,彼らを例外的に相談役等に任用する場合には,社外役員の同意を得る,業務内容や報酬(待遇)について情報開示する,任期を最高2年程度に限定するなどの措置を取ることが望ましい。
第5回は, 本事件の締めくくりとして, 監査役の機能不全と役員報酬補填問題について解説する。
【今回の要点📝】
【注釈および参考資料】
<注釈>
- この点については, 経済産業省のCGS研究会報告書も,「株主等に対して責任を負っていない相談役・顧問が,社長・CEOの選解任や経営に不当な影響力を行使している事態が生じている場合には,現役の経営陣が社内で適切なリーダーシップを発揮するという観点から問題であり,改善する必要がある。このような事態は,相談役・顧問の中でも,経営トッ プであった社長・CEO 経験者が相談役・顧問として会社に残る場合に,特に問題となり得ると考えられる」(同38頁)と指摘している。
<参考資料>
- 第三者委員会(2020)『調査報告書』(第三者委員会報告書)
- 調査委員会(2018) 『報告書』(調査報告書)
【「樋口先生の「失敗に学ぶ経営塾」WEB講座 連載一覧】
- 第1回 関西電力のコンプライアンス違反事件(全5回)
- 第2回 不正行為の自己正当化ー関西電力のコンプライアンス違反事件
- 第3回 閉鎖的な人事―関西電力のコンプライアンス違反事件
- 【本稿】第4回 調査委員会の機能不全―関西電力のコンプライアンス違反事件
- 第5回 監査役会の機能不全―関西電力のコンプライアンス違反事件(完)
- 著作権侵害事件とベンチャー経営シリーズ

博士 警察庁人事総合研究官
1961年、広島県生まれ。1984年より上級職として警察庁に勤務。愛知県警察本部警備部長、四国管区警察局首席監察官等を歴任、外務省情報調査局、内閣官房内閣安全保障室に出向。1994年に米国ダートマス大学でMBA取得。警察大学校教授として危機管理・リスク管理分野を長年研究。2012年に組織不祥事研究で博士(政策研究)を取得。危機管理システム研究学会理事。三菱地所及びテレビ東京のリスク管理・コンプライアンス委員会社外委員。一般大学で非常勤講師を務めるほか、民間企業の研修会や各種セミナーなどで年間30件以上の講演を実施。
【著作】
『ベンチャーの経営変革の障害』(白桃書房 2019)、『東芝不正会計事件の研究』(白桃書房 2017)、『続・なぜ、企業は不祥事を繰り返すのか』(日刊工業新聞社, 2017)、『なぜ、企業は不祥事を繰り返すのか』(日刊工業新聞社, 2015)、『組織不祥事研究』(白桃書房 2012)など多数。その他に企業不祥事関連の研究論文を学術誌に多数掲載。コラム「不祥事の解剖学」(ビジネスロー・ジャーナル誌)、同「組織の失敗学」(捜査研究誌)を連載中。