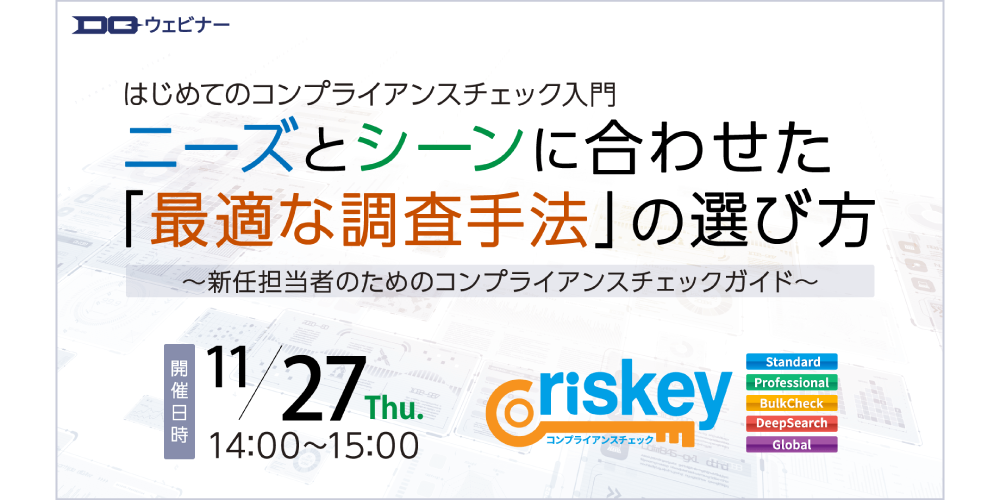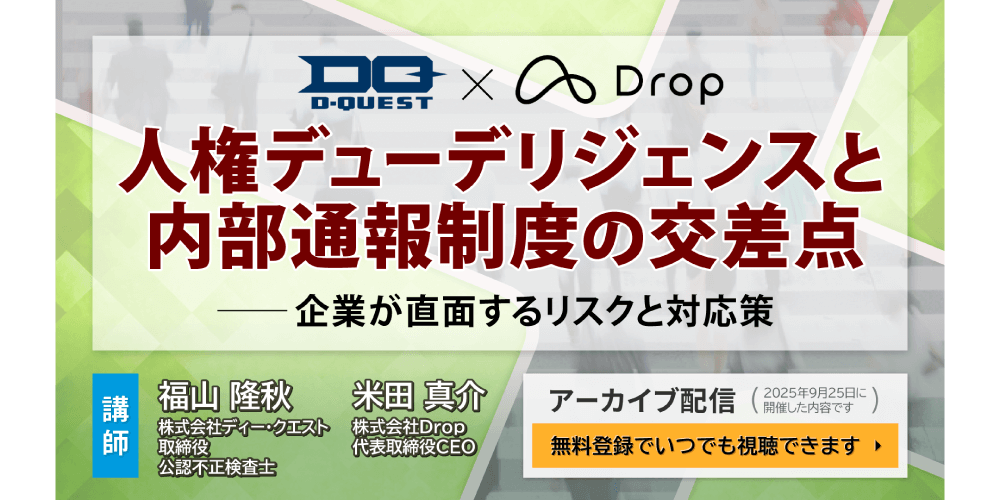DQトピックス
会計不正の類型と再発防止策 : 第3回「売上の早期計上」
2020.07.07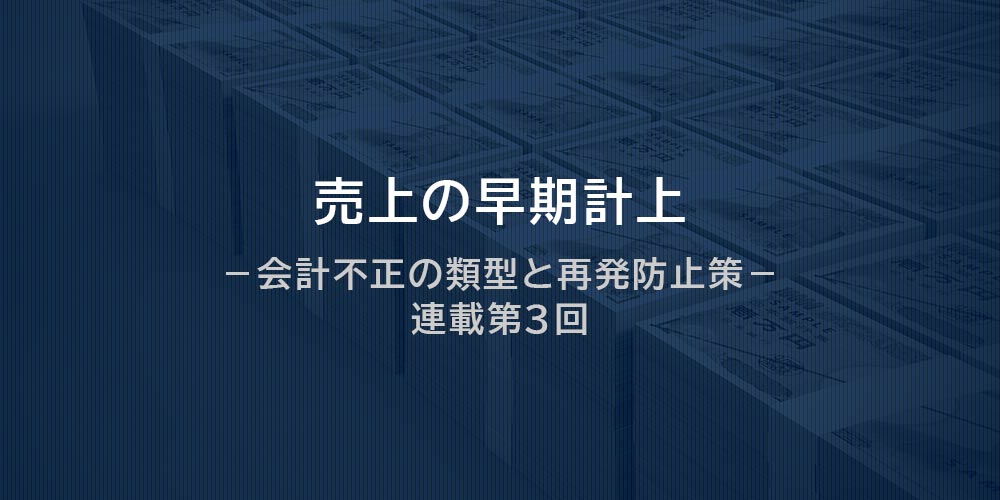
もくじ
また,2018(平成30年)年に公表された「収益に関する会計基準」との関係についても,確認しておきたい。
1.売上の計上基準=収益の認識基準
1)企業会計原則とわが国の会計慣行
まず, 企業会計原則「第2 損損益計算書原則三のB」を確認してから,本論に入りたい。
第2回の「工事進行基準」はこの規定の「ただし書き」を根拠とする収益認識であったが,今回は,前段部分の「実現主義」について検討する。「収益は実現主義,費用は発生主義」という言葉は,簿記の書学者でさえ常識となっている収益費用の計上基準を端的に表したものであるが,では,何をもって「実現」とすればいいのであろうか。
一般的な商品販売を例として考えた場合,「実現主義」の基準として以下が挙げられる。
- 商品の出荷を終えた段階(出荷基準)
- 商品が相手に到着した段階(引渡または着荷基準)
- 商品が販売先の検査に合格した段階(検収基準)
こうした基準の中でも,わが国の会計実務では,売上高の計上基準として長く「出荷基準」が認められてきた。
2)「収益認識基準」の公表
2018(平成30)年3月,企業会計基準委員会「収益認識に関する会計基準(企業会計基準第29号)¹ 」を公表した(以下「収益認識基準」と略称する)。「収益認識基準」では,収益認識を次の5段階に分けて規定している。
- ステップ1:契約の識別
- ステップ2:契約における履行義務の識別
- ステップ3:取引価格の算定
- ステップ4:履行義務への取引価格の配分
- ステップ5:履行義務の充足による収益の認識
ステップ5として,「履行義務の充足による収益の認識」が求められたことにより,「出荷基準」は収益認識基準としては不適格となるはずであった。しかし,これまでのわが国の会計慣行に与える影響を考慮して,企業会計基準審議会は,「収益認識に関する会計基準の適用指針(企業会計基準適用指針第30号)² 」の中で,「商品又は製品の出荷時から当該商品又は製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合」に限って,出荷時または着荷時に収益を認識することができるという指針を示している(適用指針98,117)。
法人税法も平成30年度改正で,「収益認識基準」を導入し,これに伴って基本通達にも大幅な改正が加えられ,改正前の法人税基本通達2-1-1は,改正後の2-1-2に規定を移管さる格好となって,次のように改められたものの,引き続き,「出荷基準」による収益認識を認めている。
2.出荷基準による売上計上が否定され,売上高の減額修正を行った事例

1)中国子会社における売上計上が否定された事例
美容器具やブランド商品の製造販売を行っているM社では,2019年1月から3月にかけて,中国子会社を通じて,中国国内向けの新しいECサイトにおける複数のパートナー会社に対して,製品を出荷して倉庫に搬入したことをもって売上計上を行っていた。監査法人は,一連の取引について,売上金額が高額であり,製品単価も通常取引より高く設定されていることから疑念を抱き,第三者委員会による調査を要請した。
第三者委員会は,調査の結果,パートナー会社から代金の支払いがないこと,パートナー会社に価格決定権がないこと,余剰在庫について返品を受け入れることで合意していたことなどから,「委託販売に類似した取引」と認定して,パートナー会社において実際に売り上げを計上した部分以外の売上を取り消すことが妥当であると結論づけている。
2)顧客から「検収書」を取得しているにもかかわらず,売上計上を否定された事例
AIを活用したデータソリューション事業を営むA社は,2019年12月期の決算時,複数の商談において、12月に請負契約を締結して期末までに作業を完了したとして売上計上を行った。これについて,監査法人から,利害関係のない外部有識者による調査・検証を求められた。
A社は,12月末現在で一部作業が終わっていないものの,業務を受託した各社との間では12月末日までの成果物の納品をもって契約の目的物とする変更を合意のもと,検収書を受領しており,請負代金も契約どおりに支払われていることから,売上計上には問題がないという見解であった。
これに対し,外部調査委員会は,調査の結果,契約にかかる作業は12月末日までに完了しておらず,同時点で契約の目的物を変更する合意が成立したとは認められないことから,2019年12月に売上を計上することは妥当ではないとの判断を示した。
3.早期発見策・再発防止策―効果的な業務監査―
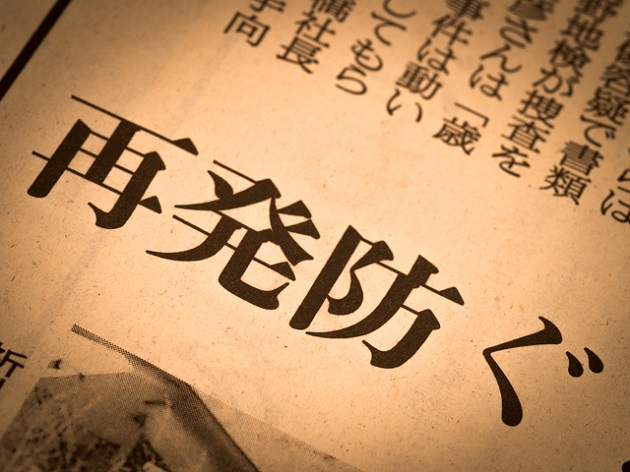
1)まずは,売上計上に関する規定の整備とその周知
会計基準の趨勢が「出荷基準」を認めない方向に動いていることは間違いなく,企業は,まず自社の売上計上基準を「検収基準」,「収益認識基準」に置き換え、「履行義務の充足による収益の認識」へと統一することが急務であろう。
そのうえで,契約上の履行義務を充足したことをどうやって立証するかという点について,会計監査人とも協議のうえで,各社の業務内容に即して規定し,営業部門にも周知しておく必要がある。さらに,「履行義務の充足による収益認識」についての理解を深めるための施策として社内研修を行うと共に,実務を担う現場に浸透しているかどうかを測る業務監査も不可欠である。

2)業務監査を通じて現場の実態を把握し,売上の計上基準を浸透させる
業務監査においては,外形的に,履行義務が充足されたことを示す書類(証跡)の有無だけを確認するのではなく,契約内容から,何をもって「履行義務が充足された」と判断できるのか,そのために必要な手続きは何かといった認識を,監査部門と現業部門とで共有し,会計監査人にも同意を得るプロセスが必要である。
なぜ,早期に売上を計上しようとするのかという動機に注目すれば,当然,「今期の業績が悪い」「もう少しで売上目標が達成できる」といった部門や担当者において,インセンティブが働くことは容易に想像できる。さらに,期末近くになって受注した商談が短期間のうちに果たして「履行義務が充足できる」契約内容であるのか否か。こうした視点から,監査対象を絞っていけば,効果的に業務監査を行うことにつながるのではないだろうか。
4.まとめー安易な早期売上計上の代償は高くつくー

「出荷基準」による収益認識から「検収基準」による収益認識へと全面的に移行し,これを浸透させることによって,早期売上の計上に対する抑止策になると同時に,第1回でとりあげた「架空循環取引」についても,売上計上は困難となり,未然防止が可能となるものと考える。
事例として紹介したM社は,中国市場における業績に支えられて売上高を伸長させ,上場を果たしたものの,上場時にはすでに業績には陰りが見えていたことがわかっている。また,A社についても,外部調査委員会によって売上計上を否定された金額を予定どおり計上できていれば,期初の業績予想が達成できていたことがわかっている。業績が下降している局面では,経営陣に,無理をしてでも売上を計上したい気持ちに傾くのは仕方がないことではあるが,その結果,M社は過年度決算の修正を余儀なくされ,A社は決算発表が3ヵ月以上も遅延し,定時株主総会は継続会となって,どちらも投資家の信用を失っている。さらに,外部の有識者による調査や追加で行われる会計監査に要する費用も,業績を悪化させることになるだろう。
担当者は,悪意もなく,ただ業績に貢献したいと考えて,安易に売上計上するための外形を整えているの過ぎないのかもしれない。しかし,安易な売上計上の代償はとてつもなく高くつくという認識を,経営陣はしっかりと持たなければならない。
参考資料
- 企業会計基準委員会「企業会計基準第 29 号 収益認識に関する会計基準」 (https://www.asb.or.jp/jp/wp-content/uploads/shueki20200331_02.pdf)
- 企業会計基準委員会「企業会計基準適用指針第 30 号 収益認識に関する会計基準の適用指針」 (https://www.asb.or.jp/jp/wp-content/uploads/20180330_03.pdf)
【「会計不正の類型と再発防止策」連載予定】

代表
ACFE JAPAN 研究会所属:東京不正検査研究会、不正の早期発見研究会
租税訴訟学会 会員
1998 年、税理士登録。1998 年 2 月から 2010 年 1 月までIT 系企業で税務、債権管理、内部統制などを担当。2010 年 1 月、税理士として独立開業。