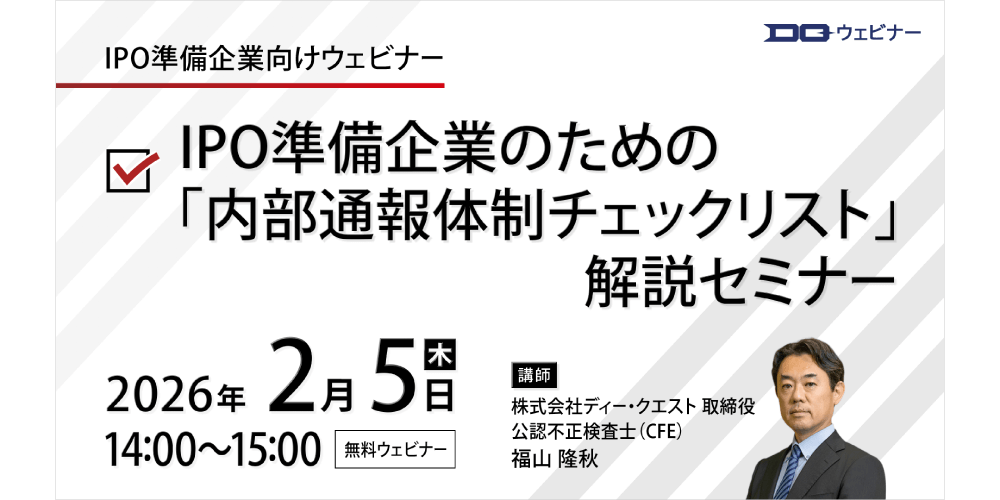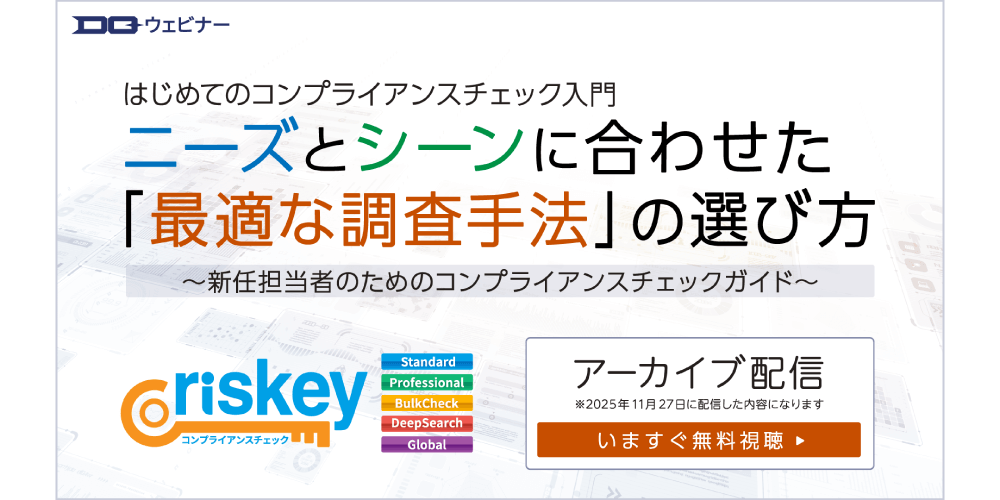DQトピックス
会計不正の類型と再発防止策 : 第4回「費用, 損失の隠蔽または先送り」
2020.07.28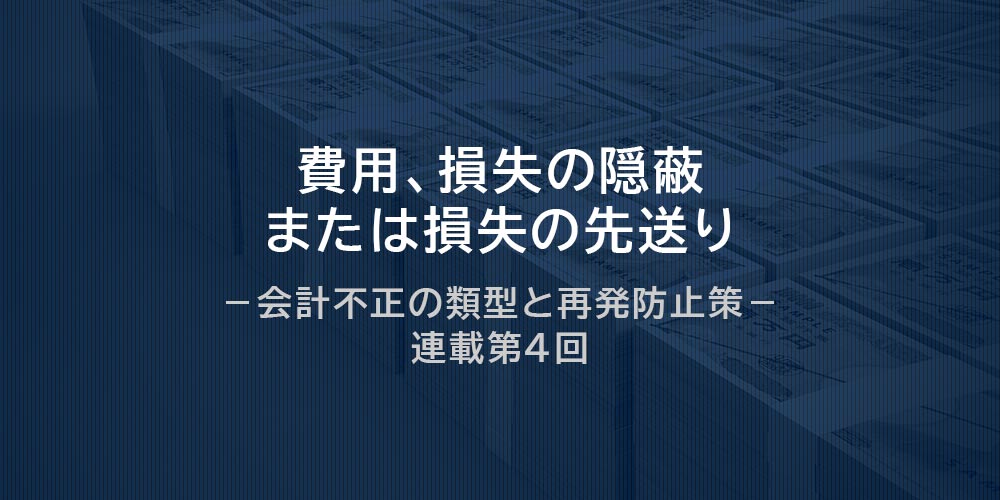
もくじ
【序章:2019年12月発覚「J社の費用, 損失の隠蔽又は先送り」】
粉飾決算の手口については,大きく分けると2種類しかないことはよく知られている。
売上原価,費用や損失の過少計上(隠蔽も含む)
過去3回の連載では,「売上高の過大計上」の例として,架空売上や早期売上について,事例を交えて検討してきたが,今回は,「費用,損失の隠蔽または先送り」による会計不正について,昨年12月に発覚した大手ディスプレイ・メーカーJ社の事案をもとに,その手口と会計不正に至った原因,発覚の経緯,再発防止策について考えてみたい。
一般的な傾向として,「売上高の過大計上」による会計不正は,営業部門が主導して行われ,「費用,損失の隠蔽または先送り」による会計不正は,管理部門,とくに経理部門が主導して行われることが多い。経理部門による会計不正の特徴は,経理知識に基づいた不正であるため,発覚しづらいことであり,本稿でとりあげるJ社においても,退職した経理部門の幹部社員が不正の内容を告白する文書を経営陣に送付したことから明るみに出たものであり,経理部門における内部牽制機能は発揮されず,また,大手監査法人による会計監査も,不正を見抜くことはできなかった。
1.元経理部門幹部社員による会計不正の手口

2019年11月26日,J社は,元経理・管理統括部長A氏から,経営陣の指示により過年度の決算について不適切な会計処理を行っていたという通知を受け,特別調査委員会による調査を経て,12月24日,第三者委員会を設置して通知に記された不適切な会計処理に関する疑義の調査を行うこととなった。
なお,A氏は,約5億7,800万円の金員等を横領していたとして,2018年12月28日,J社を懲戒解雇となっており,さらに,J社に通知を送った後,11月30日に死亡が確認されている。
A氏が通知した不適切な会計処理16項目であったが,第三者委員会は,そのうち12項目について,不適切な会計処理=粉飾決算があったことを認めている。下表の赤字の9項目が,本稿のテーマである「費用,損失の隠蔽または先送り」の類型に属する会計不正である。
- (1)100億円規模の架空在庫の計上
- (2)滞留・過剰在庫について実態と異なる販売見込み等を用いることによる評価損の計上回避
- (3)本来費用計上すべき消耗品を貯蔵品に振り替えることによる利益操作
- (4)本来計上すべき費用や損失の先送りや資産化による利益操作
- (5)海外向け販売代理店への買戻条件付販売による売上計上
- (6)大口顧客に対して販売した製品保証に関する費用の先送り
- (7)海外受託製造会社(Electronics Manufacturing Service)(以下「海外EMS」という)及び海外製造子会社におけるJDI帰責の損失に関する引当金の未計上及び先送り
- (8)固定資産の減損損失の回避
- (9)来費用処理すべきものを固定資産の取得価額に算入することによる利益確保
- (10)関係会社に対して四半期ごとに支出した研究開発委託費を出資に振り替えることによる損失回避
- (11)段階利益(利益表示区分)の操作による営業利益の過大計上
- (12)上場申請時等における実現不可能な事業計画の作成
- (1)関係会社株式の減損処理及び投資損失引当金の計上回避
- (2)不適切な繰延税金資産の追加計上による利益確保
- (3)繰延税金資産等を原資とした配当
- (4)構造改革に伴う損失を経営陣が発表した数値になるようにする操作
つまり,A氏による粉飾は,多くの手口において継続して繰り返されるのではなく,基本的には,次の四半期決算で粉飾を解消し,または段階的に粉飾金額を縮減していたことがわかっている。粉飾決算は,最初は比較的少額の利益の過大計上から始まって,徐々に金額が大きくなり,特定の勘定科目の残高が突出して増加したり,キャッシュフローが大幅に悪化したりという,粉飾の端緒に,経理部門や監査部門,会計監査人が気づくことによって明るみに出ることが多いのだが,本件では,複数の手口を使いながらも,翌期に粉飾により計上した利益を洗い替えることで,発覚を免れていた。
2.早期発見策・再発防止策
J社事案では,2012年9月に,経理・財務部ゼネラル・マネージャーとして入社したA氏に,経理部門の責任者として権限が集中し,結果的に,長期間にわたる粉飾決算が行われる一方で,巨額の資金の横領を看過していた。

1)経理部門の充実と適切なローテーション
J社では,元経理・管理統括部長A氏に経理部門の権限が集中し,取締役会による監視監督機能が発揮されていなかったことから,再発防止策としては,次の2点が真っ先に挙げられるだろう。
- ①経理部門における内部牽制機能の強化
- ②経理部門に対する経営陣と内部監査部門による監視監督機能の強化
「内部牽制絹の強化」としては,一人に権限を集中させないことと同時に,適切な人事ローテーションを行って,前任者の業務内容を検証することが必要である。
長引く景況感の悪化は,コスト部門である管理部門の人員削減へのインセンティブを経営陣に抱かせ続けており,経理部門も例外ではない。ただ,上場企業である以上,経理部門を弱体化させるようなことがあってはならない。これが再発防止策の第一歩である。

2)内部通報制度の整備,特に内部通報に対する経営陣の意識改革
次いで,本稿でも内部通報制度の重要性を挙げておきたい。J社事案でも,財務統括部の元従業員から当時の代表取締役会長に対して直接,内部通報があったにもかかわらず,経営陣は,これを元従業員の人事上の不満によるものと考えて,きちんと調査をしていなかったことが,第三者委員会から批判されている。これだけの手口の不正を行っていれば,経理部門の従業員は何らかの不審感を抱いているのは間違いない。本来であれば,経理部門内の内部牽制機能が働いて,そうした不正が抑止できればいいのだが,上長の行う会計処理に口を挟むことが難しいことは想像できる。そこで,内部牽制機能を補完する内部通報制度が必要となる。
また,当然のことだが,通報内容に予断を持って対処してしまうここと,通報者=不満分子といったレッテル貼りをしてしまうことを避けるためには,経営陣の意識そのものを変える必要があることは言うまでもない。

(3)監査役監査(経理部門の不正抑止)
さらに,監査役監査が,経理部門の不正抑止に果たす役割についても検討しておきたい。
J社第三者委員会調査報告書によると,J社の常勤監査役は,経理部門のメンバーから,当時の代表取締役会長からの業績必達のプレッシャーが厳しく,非常にストレスを感じていると聞き,危機感を抱いて,経営陣に対して,今のようなプレッシャーをかけていると経理部門のモチベーションが落ち,不正会計や内部告発のリスクがある旨を伝え,プレッシャーを緩和すること,コンプライアンス厳守を徹底することと併せて,経理部門メンバーに対して職業的倫理観を鼓舞し,適正会計を遵守するよう経営者自らの言葉で語ることを具申した,ということである。
結果的には,こうした取り組みだけで,不適切な会計処理を抑止することはできなかったが,常勤監査役が経営陣だけではなく,会計監査人や内部監査部門に対しても,同じような懸念を表明し,三様監査を進める中で共通の問題意識を持っていれば,より早く不適切な会計処理を発見できた可能性はある。何より,そうした監査役の姿勢は,経理部門に対する牽制効果となることが期待できる。
3.まとめー経営陣への過度な忖度が会計不正を招く
冒頭でも述べたように,「費用,損失の隠蔽または先送り」による会計不正は,経理部門が主導して行われることが多く,しかも,発覚しづらいという特徴を有している。経営陣からの無理難題とも言えるコスト削減や利益改善要求に対して,経理部門の責任者が,法律や会計基準を遵守することをどこまで主張できるのかというのは難しい課題である。経理部門が問題を抱え込まないためには,社外監査役や社外取締役といった,経営陣に意見を具申できる立場の人間とのコミュニケーションが重要であるが,これも理想論に過ぎない。
むしろ,本稿でとりあげたJ社事案のように,経理部門の責任者が,経営陣の意図を忖度して,具体的な指示や命令がなくても,自らの会計知識を悪用して,複数の会計不正の手口を駆使して粉飾決算をしてしまうことの方が多いのかもしれない。
そうした粉飾決算は,結果として会社の経営改善を先送りしたり,誤った方向に経営の舵を取ったりすることにつながり,かえって会社の体力を奪うのみならず,株主をはじめとするステーク・ホルダーに損害を与えるものであるということを,経営陣と経理部門の責任者が自覚し,経理部門に潜在している不正リスクをいかに軽減するかについて,コンセンサスを得ておく必要があろう。
【「会計不正の類型と再発防止策」連載予定】

代表
ACFE JAPAN 研究会所属:東京不正検査研究会、不正の早期発見研究会
租税訴訟学会 会員
1998 年、税理士登録。1998 年 2 月から 2010 年 1 月までIT 系企業で税務、債権管理、内部統制などを担当。2010 年 1 月、税理士として独立開業。