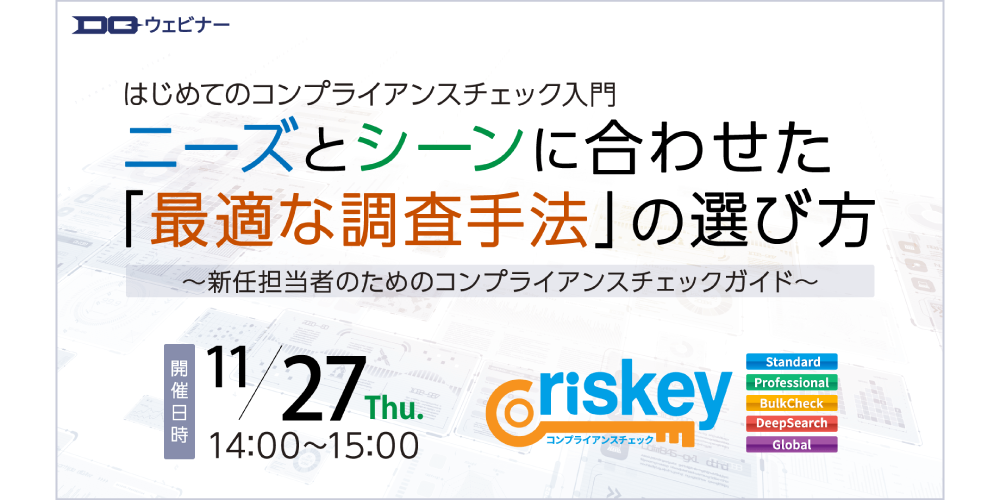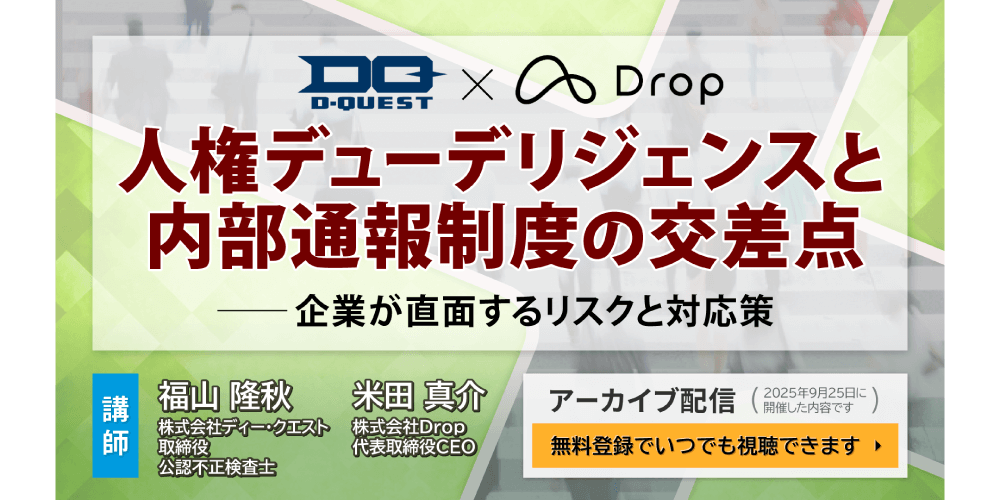DQトピックス
樋口先生の「失敗に学ぶ経営塾」WEB講座:著作権侵害事件とベンチャー経営シリーズ 第3回 事件の原因構造-リスク軽視の経営姿勢
2020.12.15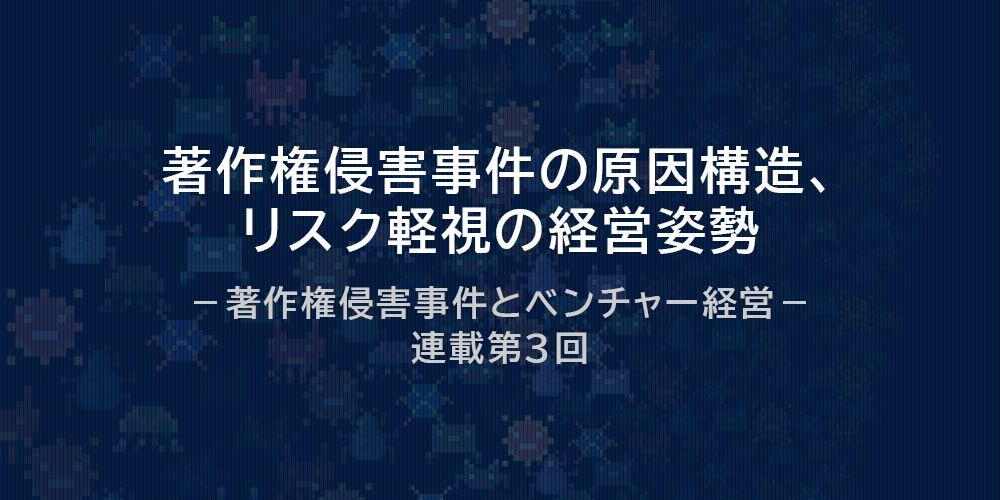
もくじ
1.コピペを誘発した事業方針

D社では、前回解説したようにSEOに拘泥するあまり、読者に良質な記事を提供するという本来の視点を見失ってしまっていた。第三者委員会報告書によれば、「(編集部は、)タイトルや見出しの訴求力だけを大事にしていた。内容よりもSEOで検索上位になることを目的にしており、内容のチェックはあまりされなかった」(同237頁)とされる。こうした品質軽視がコピペの横行を放置する土壌になった。
また、クラウドライターを使って記事を量産する方針も、やはりコピペの横行に結びついた。多数の記事を毎月新規公開した上で、サイトの採算性も確保しようとすれば、執筆単価を抑制せざるを得ない。そうした割の悪い仕事を有能な専業ライターが引き受けるはずがなく、クラウドライターへの依存度が必然的に高くなる。
低い執筆単価で一定の収入を確保しようとすれば、できるだけ沢山の記事を書かなければならないが、クラウドライターの技量は全般的に低い。また、SEOの観点から8,000字以上の記事を要求されても、それだけの長文を自力で書くのは相当な負担となる。その結果、コピペが多用されるようになった。言い換えると、D社の記事量産方針は、クラウドライターがコピペを多用することを暗黙の前提としていたのである¹。
2.成長優先・数値偏重の経営姿勢-リスク軽視
D社の企業体質は、「挑戦者としてひたすらに成長を追求する」というものであった。ネット関連のサービス事業では「Winner takes all.」(勝者がすべてを獲得する)の性格が強く、急成長してトップの座をいち早く確立しなければ生き残れなかったためである。
こうした強い成長志向がD社の躍進を支えてきたことは間違いない。しかし本事件では、コピペによる著作権侵害のリスクや、不適切な薬・医療記事のリスクを関係者が認識していたにもかかわらず、事業の成長を妨げないために、「D社は「永久ベンチャー」だからしようがない」と自己弁護して問題を放置していた。
この点について第三者委員会報告書は、「本問題は、ある意味で、D社が標ぼうする「永久ベンチャー」という理念の独り歩きによって引き起こされたという面もあるように思われる。(中略) キュレーション事業においては、それが『速ければ易きに流れてもよい』ことを意味するかのごとく曲解されて、慎重な意思決定やリスク分析がないがしろにされ、当たり前のことを当たり前にやることへの軽視に繋がってしまったような印象を受ける」(同270頁)と批判している。
3.M氏の問題点-攻めと守りのアンバランス

D社は、社長のM氏のワンマン経営であったが、同氏はキュレーション事業のリスクに関してあまりに無策であった。ネット業界では、かねてからコピペが横行し、著作権侵害に対する心理的ハードルが非常に低かった。キュレーション事業の責任者となったX氏や、過去に著作権侵害により炎上事件を起こしたY氏も、こうした業界内常識に染まっていたと考えられるが、M氏は彼らに対する監督を怠っていた。
また、SEO重視の記事量産方針を採用したことはM氏の意向であった。この方針を推進すれば、前述のとおりクラウドライターがコピペに依存することは避けられないが、M氏自身はそうしたリスクに対して鈍感だった。ちなみに、前回解説したサイト甲7の医療記事に医師監修がない問題についても、M氏は2016年夏頃に認識したが、「後で監修をつければよいではないか」と放置している。
かつてゲーム事業を大成功させた実績に鑑みると、M氏は、「攻め」=事業伸長の才覚に非常に秀でている。しかし、「守り」=リスク管理の能力については、疑問があると言わざるを得ない。そもそも同氏がコンプライアンスを軽視していた可能性さえ否定できない。
桜田(2017)は、「M社長はX氏に騙されたわけではない。X氏が描いた成長戦略にあえて乗っかっただけでしょう。著作権の問題があることは認識したうえで、とにかく記事数と利用者数を伸ばし、収益力がついたところで後から著作権問題を解決すればいい、という考えだったのだろう」(同33頁)との関係者の証言を紹介している。
4.N氏の問題点-後継者のワンマンを放任

キュレーション事業の発足時に、著作権侵害のおそれに関して質問を受けたN氏は、「それは最も重要な課題です。一番そこを気を付けています。」と回答している²。また、著作権侵害の前歴があるY氏を採用した件について、事件後にN氏は、「経営会議でも採用していいのかという議論はあった。(問題があったとすれば)採用するという意思決定よりも、採用した後にしっかり教育できたのかという部分。ただ、結果として同じような過ちを当社自身が犯してしまったのは、私どもの認識の甘さだった」と弁明している³。
ちなみに、2011年6月にN氏が後任社長にM氏を指名した事情について、H氏 は、「(N氏が)「私は、Mが社長をやってD社を引っ張っていく姿を見たいんだよね。あいつは、どうしようもないところもあるけど、ザッカーバーグ以上の経営者になれると思ってる」(と話した。) Nさんは以前からMの才能を愛していると言っていた」と記している。
創業者で大株主のN氏が過度の思い入れを持っていたことが、M氏によるワンマン経営の放任につながったと考えられる。この点について桜田(2017)は、「M独裁と言っていいほど、D社という会社はM社長のやりたい放題。NさんはM社長を後任社長に指名した手前、よほどのことがない限り、M社長の方針に背くことはない。創業者の後光が、M社長の独裁色をさらに強くしている」(同27頁。傍点筆者)との元社員の証言を紹介している。
次回は、こうした偏った経営姿勢に対して、どうしてブレーキがかからなかったのかについて解説する。
【今回の要点📝】
【注釈および参考資料】
<注釈>
- 例えば、サイト甲7の記事単価は2000字で1000円にすぎなかった。これほど低い執筆単価でオリジナルの原稿を発注するのは、常識的に考えて無理がある。
- ハフポスト2014年11月16日記事
- ねとらぼ2016年12月7日記事
<参考資料>
- 桜田徹(2017) 「村田マリの「盗用ビジネス」に50億投資「守安独裁帝国」の歪んだガバナンス」別冊宝島編集部編(2017)24-39頁
- 第三者委員会(2017) 『調査報告書(キュレーション事業に関する件)』(第三者委員会報告書)
- 春田真(2015) 『黒子の流儀』KADOKAWA
- 樋口晴彦(2019) 『ベンチャーの経営変革の障害』白桃書房
【「樋口先生の「失敗に学ぶ経営塾」WEB講座 連載一覧】
―関西電力のコンプライアンス違反事件シリーズ―
- 第1回 関西電力のコンプライアンス違反事件(全5回)
- 第2回 不正行為の自己正当化―関西電力のコンプライアンス違反事件
- 第3回 閉鎖的な人事―関西電力のコンプライアンス違反事件
- 第4回 調査委員会の機能不全―関西電力のコンプライアンス違反事件
- 第5回 監査役会の機能不全―関西電力のコンプライアンス違反事件(完)
―著作権侵害事件とベンチャー経営シリーズ―
- 第1回 ゲーム会社D社-過去の不祥事と成長最優先の企業体質
- 第2回 著作権侵害事件の概要
- 【本稿】第3回 事件の原因構造-リスク軽視の経営姿勢
- 第4回 ベンチャー起業家の弱点-経営者に忖度する心理の蔓延
- 第5回 ベンチャーの経営変革の方策-起業家自身が変革の妨げになる

博士 警察庁人事総合研究官
1961年、広島県生まれ。1984年より上級職として警察庁に勤務。愛知県警察本部警備部長、四国管区警察局首席監察官等を歴任、外務省情報調査局、内閣官房内閣安全保障室に出向。1994年に米国ダートマス大学でMBA取得。警察大学校教授として危機管理・リスク管理分野を長年研究。2012年に組織不祥事研究で博士(政策研究)を取得。危機管理システム研究学会理事。三菱地所及びテレビ東京のリスク管理・コンプライアンス委員会社外委員。一般大学で非常勤講師を務めるほか、民間企業の研修会や各種セミナーなどで年間30件以上の講演を実施。
【著作】
『ベンチャーの経営変革の障害』(白桃書房 2019)、『東芝不正会計事件の研究』(白桃書房 2017)、『続・なぜ、企業は不祥事を繰り返すのか』(日刊工業新聞社, 2017)、『なぜ、企業は不祥事を繰り返すのか』(日刊工業新聞社, 2015)、『組織不祥事研究』(白桃書房 2012)など多数。その他に企業不祥事関連の研究論文を学術誌に多数掲載。コラム「不祥事の解剖学」(ビジネスロー・ジャーナル誌)、同「組織の失敗学」(捜査研究誌)を連載中。