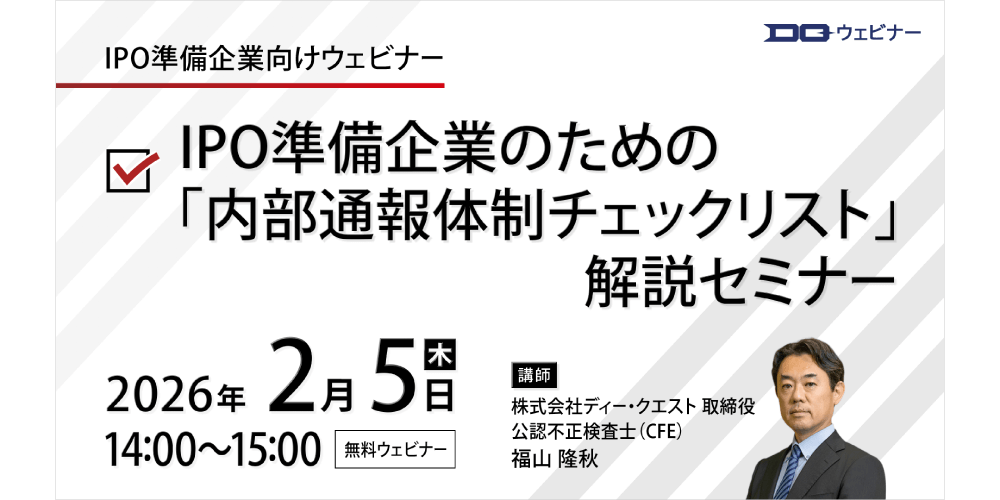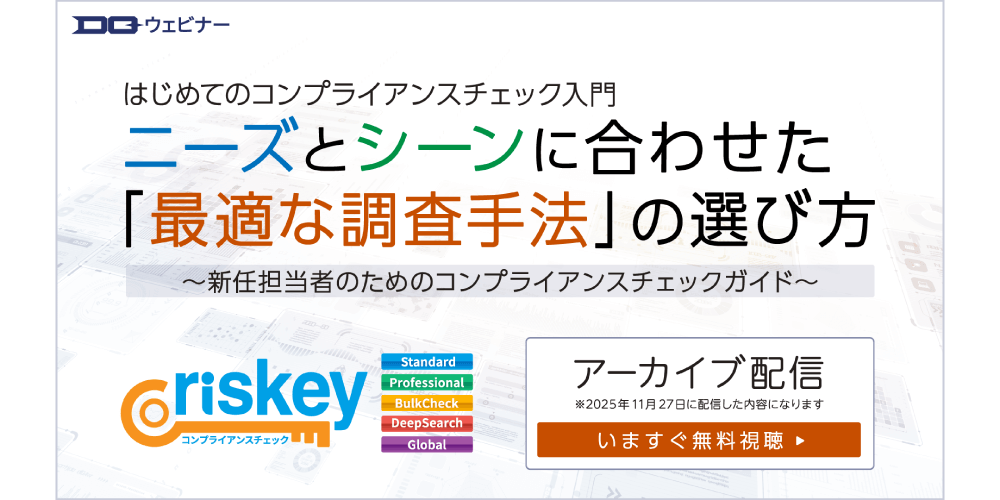DQトピックス
樋口先生の「失敗に学ぶ経営塾」WEB講座:著作権侵害事件とベンチャー経営シリーズ 第4回 ベンチャー起業家の弱点-経営者に忖度する心理の蔓延
2021.01.26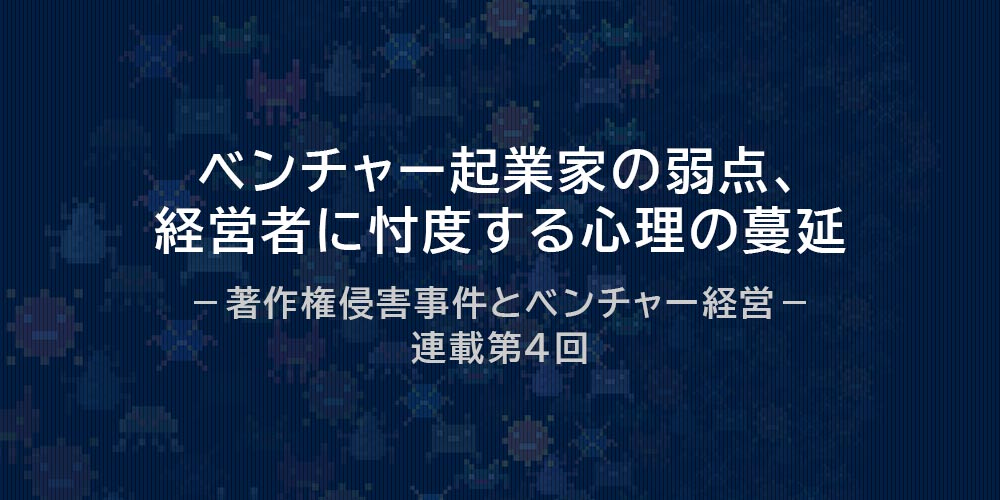
もくじ
1.リスク管理部門の機能不全

D社の法務部は、サイト甲1を買収した際のデューディリジェンスで著作権侵害のリスクを認識し、経営陣に報告した。しかし、それから後は能動的に動こうとせず、リスク管理部門としての主体性を欠いていた。前回解説したサイト甲7についても、その立ち上げの際に医師監修の必要性を表明したが、その後は放置している。こうした消極姿勢の背後に存在するのが、経営者に対する「遠慮」である。
第1回で解説したように、N氏は、X氏を登用することで、スタートアップのマインドをD社に再注入することを強く期待していた。この創業者の期待を背景に、キュレーション事業関係者が『虎の威を借る狐』と化していたのではないかと推察される。
また、事件後にN氏は、「キュレーション事業が成長し、久しぶりにうまくいっているぞとなり、管理部門も含めて組織全体が高揚していった。みんなして、もっと成功させたいという気持ちが大きくなっていたんです。その高揚に水を差したくないという心理が組織全体にかなり強く働いてしまっていた」¹と述懐している。キュレーション事業の好調な出足に経営者以下が浮き立っていたため、リスク管理部門は、「それに水を差したくない」と遠慮したのだろう。
成長を最優先にしていたD社では、もともとリスク管理部門の立場が弱く、普段から主体性を発揮できていなかった可能性が高い²。 言い換えると、リスク管理部門を機能させるには、社内でリスク管理業務の意義についての理解が浸透しなければいけない。そのためには、まず経営者自らがリスク管理を重視する姿勢を示すことが必要である。
2.H氏の退職
N氏の「守り」の面での能力不足を補っていたのが、2015年に退職したH氏であった。
D社におけるH氏の役割について、N氏自身が、「現場がアクセルをふかしたくなるときに警報を鳴らしてくれる存在で、彼の鳴らす警報を皆が注意して聞いていた」と述懐している。
このようにH氏が属人的にリスク管理面を補佐していたところ、同氏の退職により経営陣のリスク管理能力の不足が顕在化したのである。この点に関して第三者委員会報告書は、「全社横断的に事業のコンプライアンス及びリスク管理上の問題点を把握し、改善を提言し実施していく、事業の推進者とは独立した思考ができる強い権限をもった役員レベルの者は存在していなかった。もしこのような者が存在していれば、早期に本問題の芽を摘むことができたのではないかと思われる」(同273-274頁)と指摘している。
3.社外役員の機能不全

第三者委員会報告書は、「取締役会や監査役会においては、キュレーション事業は順調に成長しているという収益面ばかりが報告され(た)」(同268頁)としている。しかし、キュレーション事業がゲーム事業に次ぐ新しい柱として期待されていた以上、社外取締役としては、そのリスクについても当然に関心を持つべきであった。実際にも、サイト甲1買収時に取締役会で著作権侵害リスクに関する説明がなされていたのに、その後に取締役会で報告を求めたことはなく、また、議論をした形跡も見当たらない³。
本事件に対するM氏の責任は明白であるが、事件後にM氏が代表取締役に留任した件について、取締役会で異論が提起された形跡がないのも不可解である。そもそも第1回で説明したように、M氏が担当していた米国事業で巨額損失が発生したことを勘案すると、社外取締役としては、この機会にM氏の経営手腕を疑問視してしかるべきであった。
D社では、社外取締役による企業統治が機能していなかったと言わざるを得ない。その背景について桜田(2017)は、「社外取締役の2名は、いずれもN会長が長年にわたって口説き落とした面々で、N会長の意に背くようなことはしない」(同38頁)と指摘している。
4.ベンチャー企業のリスク-急成長に追いつけない組織

以上のとおり、N氏を補佐していたH氏の退任と、社外取締役による企業統治が機能不全に陥っていたことにより、経営陣のリスク管理能力の未熟さが露呈した。これと同様のケースが、他の著名なベンチャー企業でも散見される。
N氏が高く評価していたFacebookの創業者のザッカーバーグ氏は、大量の個人情報が不正に流出したことを2015年に認識しながら、その追及を懈怠するとともに、2018年まで流出の事実を公表しなかった。また、ライドシェア最大手のウーバーテクノロジーズでは、2017年に創業者のカラニック氏が不祥事により辞任に追い込まれている。
急成長を遂げたベンチャー企業で、リスク管理の不手際によって不祥事が発生する事情として、「急激な拡大による歪み」と「経営方式の変革の遅れ」が挙げられる。
前者の「急激な拡大による歪み」に関しては、大和銀行ニューヨーク支店巨額損失事件を分析した樋口(2006)が、不正の舞台となったカストディ(証券保管)係の業務量が3年間で20倍以上に膨張していたことに注目して、「業務負担やその重要性が急速に拡大している部署において、リスク管理体制のレベルと実際の業務内容とのバランスが一時的に崩れる危険性が認められる」(同68頁)と指摘している。急速に成長している企業あるいは事業分野では、リスク管理体制が規模の拡大に追いつかなくなるおそれがあることに留意する必要がある。
後者の「経営方式の変革の遅れ」に関しては、ベンチャー起業家は、「攻め」を重視するあまり、「守り」であるリスク管理を軽視する傾向が認められる。事業の立ち上げ時にはそれもやむを得ないが、事業が成功して規模が拡大した後は、「守り」の面でもバランスを取ることが要請される。しかし現実問題として、起業家が自己変革を図るのは容易でない。この問題については、次回に詳しく述べる。
【今回の要点📝】
【注釈および参考資料】
<注釈>
- 日経ビジネス2017年10月9日号記事
- このようにリスク管理部門の存在感が希薄であったことが不祥事に結びついたケースとして、ベネッセ顧客情報漏えい事件が挙げられる。
- 格付け委員会の久保利英明委員も、「ゲーム事業に代わる収益の柱として位置づけられているにもかかわらず、なぜ取締役会で議論されなかったのか。これこそが調査対象の本筋である。社外取締役や監査役がこれらに関心を持たなかったとすれば、重大なガバナンス上の欠陥と言わざるを得ない」(格付け委員会(2017), 3頁)と批判している。
<参考資料>
- 桜田徹(2017) 「村田マリの「盗用ビジネス」に50億投資 「守安独裁帝国」の歪んだガバナンス」別冊宝島編集部編(2017)24-39頁
- 第三者委員会(2017) 『調査報告書(キュレーション事業に関する件)』(第三者委員会報告書)
- 第三者委員会報告書格付け委員会(2017) 『第13回格付け 総合評価』
- 春田真(2015) 『黒子の流儀』KADOKAWA
- 樋口晴彦(2006) 「大和銀行ニューヨーク支店巨額損失事件の研究(下)」『捜査研究』55(2), 67-71頁
- 樋口晴彦(2015) 「ベネッセ顧客情報漏えい事件の事例研究」『千葉商大論叢』53(1), 155-171頁
- 樋口晴彦(2019) 『ベンチャーの経営変革の障害』白桃書房
【「樋口先生の「失敗に学ぶ経営塾」WEB講座 連載一覧】
―関西電力のコンプライアンス違反事件シリーズ―
- 第1回 関西電力のコンプライアンス違反事件(全5回)
- 第2回 不正行為の自己正当化―関西電力のコンプライアンス違反事件
- 第3回 閉鎖的な人事―関西電力のコンプライアンス違反事件
- 第4回 調査委員会の機能不全―関西電力のコンプライアンス違反事件
- 第5回 監査役会の機能不全―関西電力のコンプライアンス違反事件(完)
―著作権侵害事件とベンチャー経営シリーズ―
- 第1回 ゲーム会社D社-過去の不祥事と成長最優先の企業体質
- 第2回 著作権侵害事件の概要
- 第3回 事件の原因構造-リスク軽視の経営姿勢
- 【本稿】第4回 ベンチャー起業家の弱点-経営者に忖度する心理の蔓延
- 第5回 ベンチャーの経営変革の方策-起業家自身が変革の妨げになる

博士 警察庁人事総合研究官
1961年、広島県生まれ。1984年より上級職として警察庁に勤務。愛知県警察本部警備部長、四国管区警察局首席監察官等を歴任、外務省情報調査局、内閣官房内閣安全保障室に出向。1994年に米国ダートマス大学でMBA取得。警察大学校教授として危機管理・リスク管理分野を長年研究。2012年に組織不祥事研究で博士(政策研究)を取得。危機管理システム研究学会理事。三菱地所及びテレビ東京のリスク管理・コンプライアンス委員会社外委員。一般大学で非常勤講師を務めるほか、民間企業の研修会や各種セミナーなどで年間30件以上の講演を実施。
【著作】
『ベンチャーの経営変革の障害』(白桃書房 2019)、『東芝不正会計事件の研究』(白桃書房 2017)、『続・なぜ、企業は不祥事を繰り返すのか』(日刊工業新聞社, 2017)、『なぜ、企業は不祥事を繰り返すのか』(日刊工業新聞社, 2015)、『組織不祥事研究』(白桃書房 2012)など多数。その他に企業不祥事関連の研究論文を学術誌に多数掲載。コラム「不祥事の解剖学」(ビジネスロー・ジャーナル誌)、同「組織の失敗学」(捜査研究誌)を連載中。